
コラム

受発注業務を効率化する方法とは?
業務改善のコツや専用システムについて解説
2024.02.29|最終更新日:2024.02.29

受発注に関する業務を効率化したいと思っていても、どこから手をつけてよいか悩んで、最初の一歩を踏み出せないでいる事業者は少なくないでしょう。しかし、従来の電話やFAX、メールを利用した受発注業務は、受注する側にとって多くの負担がかかり、効率化が難しいものでした。
しかし、新しいテクノロジーを利用することで、受発注業務の効率化は可能です。ここでは受発注業務における課題を挙げるとともに、課題を解決するヒントを解説します。受発注業務を効率化して、コア業務に集中できる環境をつくりましょう。
目次

1.受発注業務の課題
まずは、現状の受発注業務における課題からみていきます。
1-1.電話・FAX・メール…受注方法が多く煩雑になりがち
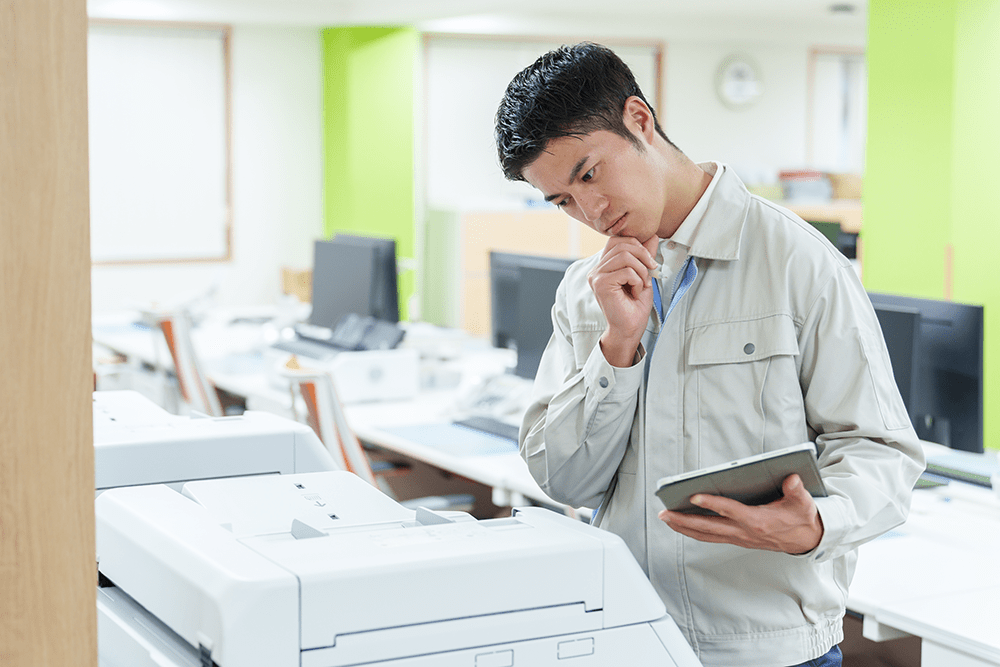
従来の受発注業務は、主に電話やFAXで行われていました。また、Eメールでの発注を行っているケースもあるでしょう。
電話やFAX、メールで受注するメリットは、特別な機器がいらず、主に発注側が使い慣れている方法で発注できることにあります。長い付き合いの得意先とは、電話での「いつもの頼むね」といった簡単なやりとりで受注が完了するケースもあることでしょう。
しかし、受注側は、電話やFAX、メールなどバラバラな方法で受けた発注を、自社の管理システムに入力する必要があります。メールの場合は記入用のフォーマットを作成し、管理システムに入力しやすい書式にすることができますが、電話やFAXで受けた発注は受注側があらためて手打ちしなければなりません。
こうした入力にかかる労力は、受注が増えれば増えるほど負担になります。せっかく受注が増えても、他の業務に影響が出たり、残業が増えたりといったことが起きがちで、素直に喜べない…といった状況を経験したことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか
1-2.電話での発注は特に属人化しやすい
電話での発注の場合、長い付き合いの得意先になるほどお互いの認識に頼った簡単なやりとりになりがちです。発注側にしてみれば「いつもの」で済むため手間がなくラクですし、「ツーカーの仲」といえば聞こえがよいのは事実です。しかし、こうした方法は仕事が属人化しやすいというデメリットがあります。
受発注業務が属人化すると、担当者が休暇などで不在の際に間違いが起こりやすくなります。例えば、社内で認識していた「いつもの発注」は30個だったので30個で手配を行ったら、実は数週間前に40個に増えていて、担当者以外は知らなかった…といったことが起こり得ます。
また、属人化した状態で担当者が異動や退職することになると、引き継ぎ作業が膨大になります。得意先に対して迅速に対応できなくなるばかりか、配置転換もしづらくなり、組織の柔軟性も損なわれてしまう可能性があります。
1-3.聞き間違いや読み間違いで受発注ミスが起こる
電話での発注は、聞き間違いによるミスが起こりやすくなります。通話内容を録音していなければ、いわゆる「言った言わない」になってしまうこともあり、齟齬(そご)があってもどちらの間違いかわかりません。また、電話をしながら書いた受注メモの存在をうっかり忘れてしまうこともあるでしょう。
こうした問題はFAXで発注を受けることで解決しますが、今度は送信状態が悪く字がかすれていたり、字が読みづらかったりといった理由で読み間違える可能性があります。また、送られてきたFAXをいつもと違う場所にうっかり置いてしまって、処理を忘れてしまうケースもあるでしょう。やはりミスをする危険が少なからず残る方法です。

2.受発注業務を効率化する方法
では、受発注業務を効率化するにはどのような方法が考えられるでしょうか。ここでは導入難易度が低い順に説明します。
2-1.電話をやめ記録が残る方法で受注する
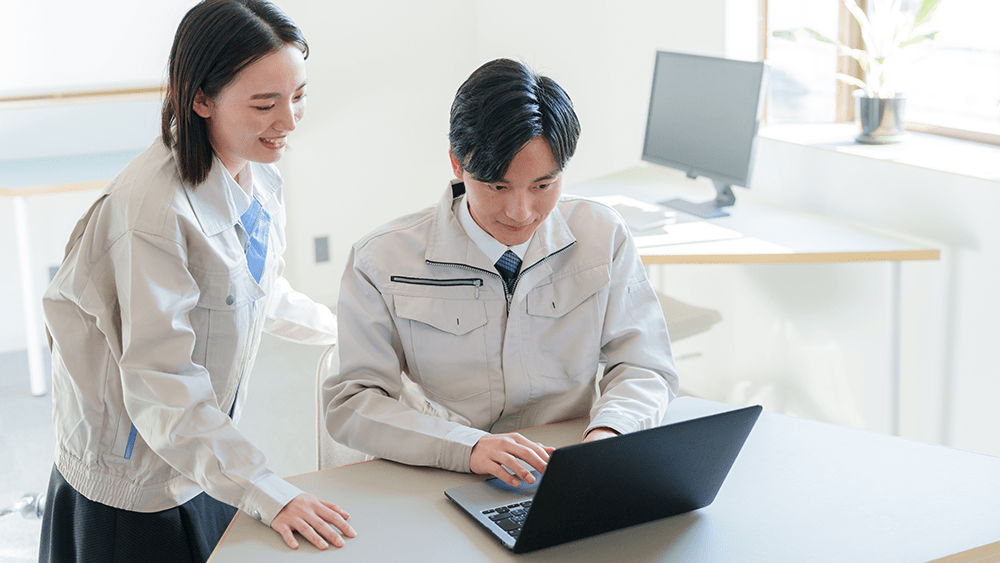
電話での「いつものでお願い」といった不確実な発注や、「言った言わない」で揉めることをなくすため、電話での発注をやめ、FAXやメールなど記録が残る手段に切り替える方法です。受注自体は電話のほうがスピーディーですが、トラブルが減りトータルでの効率がアップします。
業務中に電話が鳴ることも少なくなるため、電話対応に割かれる時間が少なくなり業務に集中しやすくなります。可能であれば、紛失の恐れがあるFAXではなく複数の社員で確認できるメールでの発注に絞るとミスが減らせるでしょう。
FAXやメールで受注する場合は、記入用の書式、もしくは入力フォーマットを簡素化して、発注者が理解しやすい明確な形式にすることも大切です。記入間違いが減るほか、問い合わせの電話も減らせます。一方で、FAXとメールの両方の状況を監視し、自社の管理システムに手入力を行う手間はなくせません。
2-2.表計算ソフトやオンラインフォームを活用する
電話に加え、FAXやメールでの発注を廃止し、Microsoftのエクセル(Excel)などを利用して発注用のファイルをつくる方法です。発注する側は発注用ファイルに内容を入力してメールで送ります。
エクセルは経理業務などでも広く利用されているソフトのため、対応可能な得意先は比較的多いでしょう。また、エクセルに似た機能がオンライン上で使えるGoogleスプレッドシートを利用すれば、エクセルを持っていない人も利用できます。
もうひとつが、オンライン入力フォームを活用する方法です。Googleフォームなど無料で利用できるものもあれば、さまざまなテンプレートが用意された有料サービスもあります。アンケートに答えるような感覚で入力をすればよく、受注側は結果をデータとして受け取れます。
表計算ソフト(エクセル、Googleスプレッドシートなど)やオンライン入力フォーム(Googleフォームなど)を利用するメリットは、受注側のフォーマットが統一されるため、データ化しやすくなることです。また、打ち間違いによるミスも減らせます。しかし、データを管理システムに入力、もしくはコピー&ペーストする手間が残るため、間違いをゼロにすることはできません。
2-3.受発注システムの導入
受発注業務がもっとも効率化できるのは、受発注システムを導入する方法です。発注側は発注専用のオンラインページなどへアクセスして発注を行い、受注側は専用の管理画面で内容を確認します。
導入するシステムにもよりますが、得意先が発注した内容をはじめからデータとして受信し、そのデータは元々の管理システムに連携できるため、メモやFAX、メールを見ながら手入力する作業が不要になり入力ミスをなくせます。また、メモやFAXを紛失することもなくなるため、受発注業務にかかる手間を大幅に軽減できます。
受発注システムは、毎月利用料がかかる製品・サービスが多くなっていますが、受発注に関わる業務量が減り、残業が少なくなるなどの効果が見込まれるため、トータルで見たときにコストを削減できる可能性は高くなります。ミスによる再配達などの手間も少なくなり、業務に余裕ができるでしょう。
3.受発注システムで効率化をするメリット
受発注業務を効率的に行うためには、受発注システムの導入がもっとも効果的です。では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
3-1.発注の正確性が向上する

電話による口頭での発注は誤解が生じやすく、FAXやメールの場合も入力ミスを完全になくすことは難しいでしょう。しかし、受発注システムを利用すれば、発注する得意先が直接商品を選んで必要な情報を入力するため、ミスのリスクが減少し発注の正確性が向上します。
導入には得意先の理解が必要にはなるものの、ミスが減ることで得意先からの信用がアップするほか、業務フローが大きく改善する期待が持てます。
3-2.他の業務に集中しやすくなる
受発注システムを導入すると、電話、FAX、メールなど、バラバラだった受注方法が一本化され、業務がシンプルになります。また、受発注に関する電話対応が大幅に減り、FAXやメールの受信確認もこまめに行う必要がなくなるため、他の業務に集中できるようになります。
今まで発注ミスが起こりがちで、得意先への再配達などで人手が取られがちだった場合は、それらの手間も減らせることになります。受発注業務に必要な時間が短くなるぶん、今まで優先順位が低くなりがちだった重要な業務にも取り組めるようになるでしょう。
3-3.コスト削減に繋がる
受発注システムを導入することでコスト削減も可能になります。FAX発注用紙を印刷して得意先に渡すコストや、受信したFAXの用紙代を削減できるほか、発注内容が曖昧なときに確認のために掛けていた電話代も削減できるでしょう。
受発注業務にかかる時間が少なくなれば、残業が減って人件費の削減にも繋がります。それをそのまま増益と捉えることもできますし、卸価格に反映させることもできるでしょう。これは、受発注システムを導入するために得意先を説得する際の材料にもなります。
得意先の中には、「うちには何もメリットがない」と新しい発注方法に難色を示す事業者もいるかもしれません。しかし、2023年に顕著に起こった食材卸価格の上昇を多くの飲食店経営者が経験した今、「コスト削減のための業務改善」であることをアピールすれば、同意を得られる可能性は高くなるはずです。
まとめ
電話、FAX、メールなどを併用する受発注業務は、業務フローが複雑になりやすく、多くの手間がかかります。また、入力ミスが発生しやすいなどのデメリットもあるため、何らかの方法で効率化を考えることが大切です。
専用システムを利用した受発注業務の改善は、受発注業務のDX(デジタル・トランスフォーメーション)としても注目されています。業務フローを最適化することで、受発注業務にかかる手間は最小化され、後回しになってしまっていた大切な業務に力を注ぐことができるようにもなるでしょう。経営改善の一環として、受発注業務の効率化を検討してみてはいかがでしょうか。
受発注業務の効率化にカシオの「BC受発注」
カシオのBC受発注は、受発注業務の効率化に最適です。得意先から発注が来るとメールや画面上のアラートでお知らせするので、うっかり忘れることがなくなり、内容を確認したら「受注取り込み」をクリックするだけで販売管理システムに発注データを自動連携できます。
電話やFAX、メールなどバラバラな手段で発注を受ける必要がなくなり、入力にかかる手間も大幅に削減できます。さらに、受注した後の入力ミスも起こらなくなるため、得意先からの信頼もアップするでしょう。
発注を行う得意先は、パソコンやタブレット、スマートフォンから専用ページにアクセスして発注すればよく、得意先ごとの商品マスタも用意できるため、操作は難しくありません。従来の発注方法からの切り替えもお願いしやすくするツールも揃っており、スムーズに受発注業務のDX化を進められるはずです。
以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://web.casio.jp/bc-order/
