
コラム

Web-EDIシステムとは?
導入のポイントやメリットを解説
2024.03.29|最終更新日:2024.03.29

業務のデジタル化が進むなかで、発注書、請求書、納品書などのビジネス文書を効率的にやりとりする「Web-EDIシステム」が注目されています。
Web-EDIシステムは、これまで使われてきたEDIシステム、インターネットEDIに続く新世代のシステムであり、導入のしやすさが特長です。そのため、これまで書類を郵送やFAXでやりとりしてきた企業にとっても、DX化のひとつとして検討する価値があるでしょう。
このコラムでは、Web-EDIの基本や導入時の注意点などを紹介しながら、Web-EDIシステムがもたらすビジネス上のメリットを詳しく掘り下げます。
目次

1.Web-EDIシステムとは?
まずは、Web-EDIシステムがどのようなものかを解説します。
1-1.一般的なインターネット回線とウェブブラウザを利用するEDI
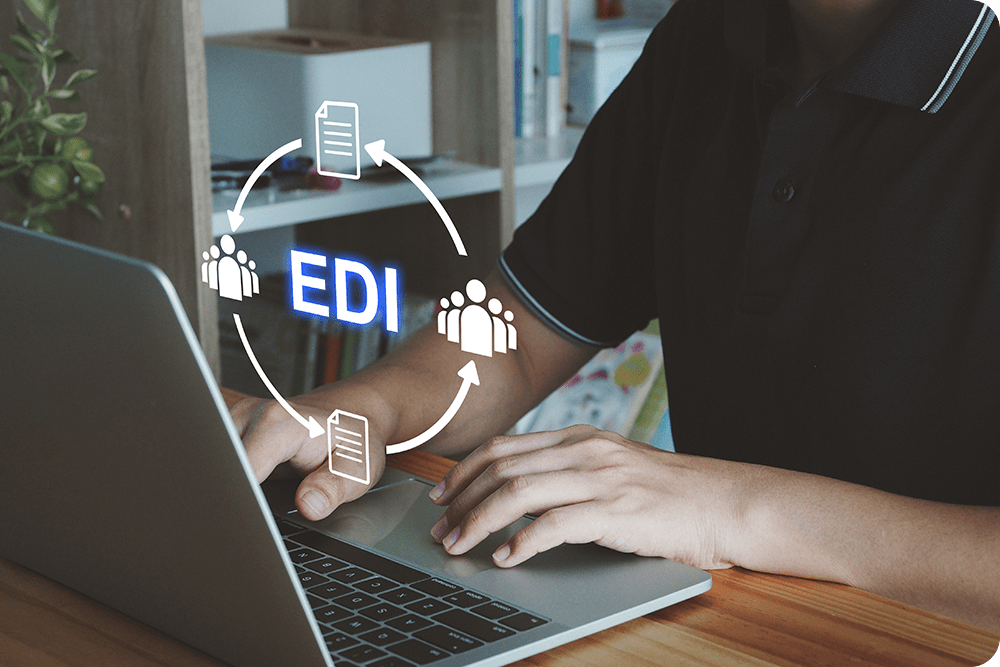
企業や行政機関では、EDI(Electronic Data Interchange)という仕組みを使って、取引で発生する帳票をやりとりすることがあります。1970年代にはじまり、1990年代には電話回線やISDN回線を使用した通信方法から、インターネット回線を使ったものへの移行がはじまりました。
そして、現在日本で主流になりつつあるのが「Web-EDIシステム」です。インターネット回線とパソコンなどのWebブラウザを利用して、発注書、請求書、納品書などのビジネス文書をやりとりするもので、専用の回線やシステムが不要なことから、導入コストが低く抑えられる特長があります。
1-2.インターネットEDIとの違い
Web-EDIシステムと混同されやすいものに、「インターネットEDI」があります。インターネットEDIもインターネット回線を利用するEDIシステムですが、1990年代から利用が開始されており、規格としては古いものとなります。しかし、通信プロトコルが標準化されていることから互換性が高く、他社と取引しやすいメリットがあります。
一方、Web-EDIシステムは一般的なインターネット回線を利用しており、通信プロトコルが標準化されていません。専用回線が必要ない代わりに、システムに互換性がない得意先の場合は、個別に対応する必要があるなどの違いがあります。

2.Web-EDIシステムを導入するメリット
Web-EDIシステムには、従来のEDIシステムにはないさまざまなメリットがあります。ここでは代表的な4つのメリットを紹介します。
2-1.専用回線いらずでインストール作業も不要
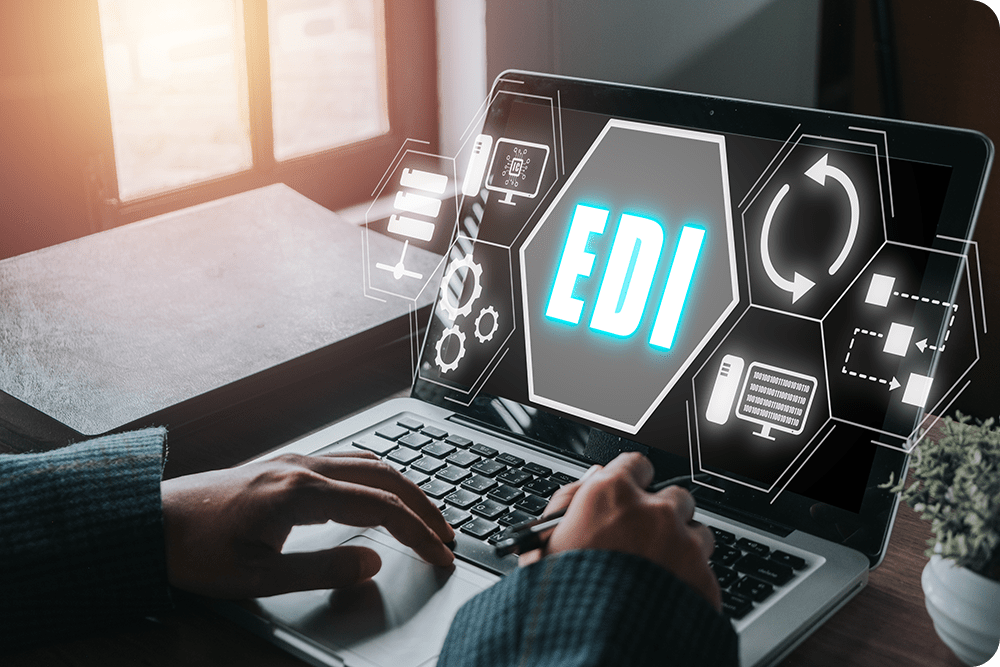
Web-EDIシステムは専用回線が必要ありません。従来のEDIシステムでは専用回線を引くための初期費用が発生していましたが、Web-EDIシステムは一般的なインターネット回線を利用するため導入が簡単です。
また、従来のEDIシステムは、パソコンに専用ソフトウェアをインストールする必要があり、定期的なアップデート作業も発生していましたが、Webブラウザを利用するWeb-EDIシステムはこうした作業も不要となります。導入のシンプルさや、維持にかかる手間の少なさは、業務の省力化に寄与するでしょう。
2-2.導入コストが低い
Web-EDIシステムは、専用の回線やソフトウェアが不要なため、導入や運用にかかるコストが低く抑えられます。特に、ISDN回線を利用する従来型のEDIシステムは、接続時間で通信量が計算されていたので、定額の光回線を利用できるWeb-EDIとは大きな違いが生まれるでしょう。
パソコンやインターネット回線は、業務のためにすでに導入済みの企業がほとんどですので、Web-EDIシステムのためにハードウェアを追加購入する費用は、ほとんどの場合かからないと考えてよいでしょう。
2-3.ペーパーレス化に寄与する
これまで、発注書や請求書などの書類を郵送やFAXでやりとりしてきた会社は、Web-EDIシステムを導入することでペーパーレス化を実現できます。書類が減ることで管理する手間も少なくなり、書類を保管するスペースもコンパクトにできるでしょう。
また、文書の印刷や郵送、またはFAX用紙やトナーにかかっていたコストが削減でき、文書を紛失してしまうリスクも低減します。業務効率化と低コスト化が実現できるでしょう。
2-4.セキュリティに優れている
Web-EDIシステムでは、SSL(Secure Socket Layer)という暗号化された通信を行います。万が一情報が漏れても、第三者では解読できない仕組みになっているので、情報漏洩のリスクは非常に低いといえるでしょう。
ただし、パソコンなどWeb-EDIシステムを使用する端末のセキュリティ対策は必要です。専用のソフトを導入したり、セキュリティルールを策定することで、非常に安全な取引が可能になります。
3.Web-EDIシステム導入のポイント
ここからは、Web-EDIシステムを導入する際のポイントを解説します。
3-1.社内システムとデータ連携できるものを選ぼう
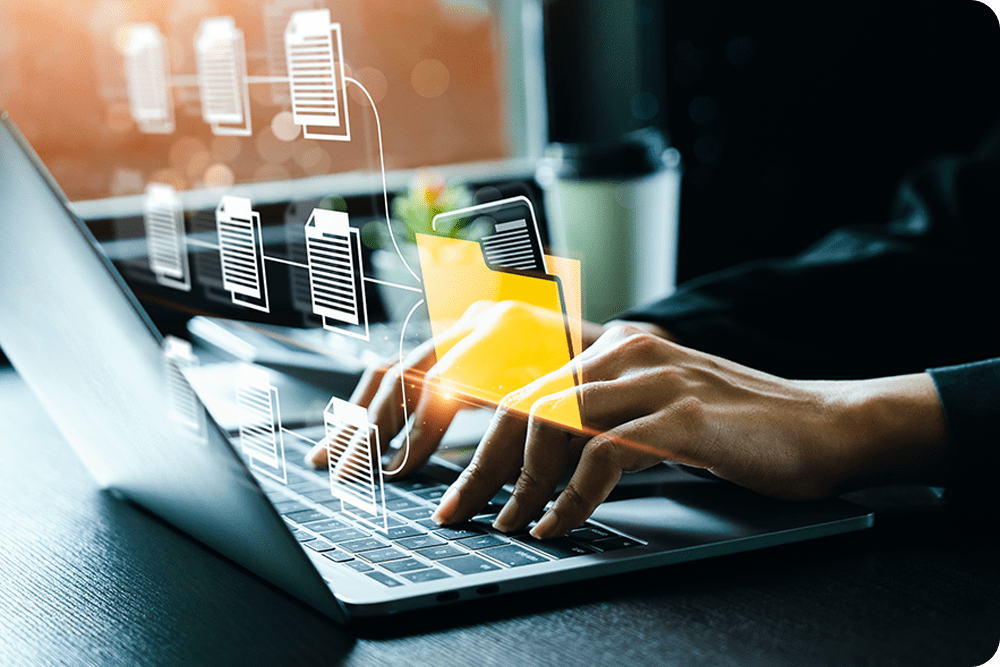
Web-EDIシステムが、社内で使用している基幹システムなどと連携できない場合があります。
連携できなくてもWeb-EDIシステム自体は機能しますが、会計処理などを行う場合に別途処理が必要になるため、作業の手間が増え、ヒューマンエラーが起きる可能性も高くなります。
そのため、Web-EDIシステムを導入する時点で、使用している基幹システムなどとの連携が可能かをチェックし、問題なく連携できるWeb-EDIシステムを選ぶことが大切です。
3-2.得意先のシステムに対応しているものを選ぼう
Web-EDIシステムは、得意先が対応していないと利用できません。Web-EDIシステムを導入するときは、はじめに得意先が対応できる仕様を確認しましょう。
対応していない得意先とは、Web-EDIシステムを利用せず個別対応を行うことになります。その得意先だけ紙ベースのやりとりが必要になったりするため、業務効率が下がり、Web-EDIシステムを導入するメリットが薄れてしまいます。
管理の複雑化や作業負担の増加を招くこともあるため、得意先との事前の調整や、柔軟に対応可能なWeb-EDIシステムを選択することも大切です。
3-3.電子帳簿保存法への対応についても確認しよう
Web-EDIシステムを利用した取引は、電子帳簿保存法の「電子取引」に該当します。電子帳簿保存法とは、電子取引した帳票類をデータのまま保存することを義務付けるものです。
Web-EDIシステムは、原則としてデータの修正削除ができないか、修正削除の記録が残るため、特別な作業はしなくても電子帳簿保存法の要件を満たしています。そして、社内の基幹システムや会計システムなどを連携する場合、そちらも電子帳簿保存法に対応したものを選ぶと、より効率がよくなります。
Web-EDIシステム導入時は、Web-EDIシステムに加え、連携するシステムが電子帳簿保存法に対応しているかもチェックしましょう。
3-4.サポート体制が充実したものを選ぼう
Web-EDIシステムを導入してしばらくは、操作に慣れず、使い方に戸惑うこともあるでしょう。そのため、サポート体制を重視して選ぶことも必要です。営業時間中に電話で質問ができる窓口があれば、より安心して導入できるのではないでしょうか。
さらに、トライアル期間が設けられているWeb-EDIシステムであれば、導入前に使用感を確認できます。普段業務に使用しているパソコンで快適に作業できるか確認できるので、失敗が少なくなるでしょう。
まとめ
Web-EDIシステムは、比較的簡単に、かつ低コストで導入できるため、業務効率化を目指す多くの企業にとって魅力的なツールといえるでしょう。
導入時には注意点もありますが、ここで紹介したことを丁寧にチェックすることで、失敗は防げるはずです。Web-EDIシステムを導入して、日頃の業務を効率化し、競争力の向上につなげましょう。
受発注業務の効率化にカシオの「BC受発注」
カシオのBC受発注は、受発注業務の効率化に最適です。得意先から発注が来るとメールや画面上のアラートでお知らせするので、うっかり忘れることがなくなり、内容を確認したら「受注取り込み」をクリックするだけで販売管理システムに発注データを自動連携できます。
電話やFAX、メールなどバラバラな手段で発注を受ける必要がなくなり、入力にかかる手間も大幅に削減できます。さらに、受注した後の入力ミスも起こらなくなるため、得意先からの信頼もアップするでしょう。
発注を行う得意先は、パソコンやタブレット、スマートフォンから専用ページにアクセスして発注すればよく、得意先ごとの商品マスタも用意できるため、操作は難しくありません。従来の発注方法からの切り替えもお願いしやすくするツールも揃っており、スムーズに受発注業務のDX化を進められるはずです。
以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://web.casio.jp/bc-order/
