
コラム

手書きでのFAX注文はデメリットだらけ?
FAXでの受発注から卒業する方法
2024.05.29|最終更新日:2024.05.29

発注の際、用紙に内容を手書きして、FAX注文しているケースはまだまだ多いはず。パソコンなどが苦手な得意先でも、簡単に使える手軽さがメリットですが、業務効率の低さやヒューマンエラーのリスクなど、さまざまなデメリットがあることも事実です。
このコラムでは、手書きFAX注文のデメリットを解説するとともに、より効率的で正確な受発注業務を実現する「受発注システム」の導入メリットについても紹介します。受発注業務を改善したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次

1.手書きでのFAX注文のデメリットとは?
1-1.手書きFAXでの注文は業務効率が低い
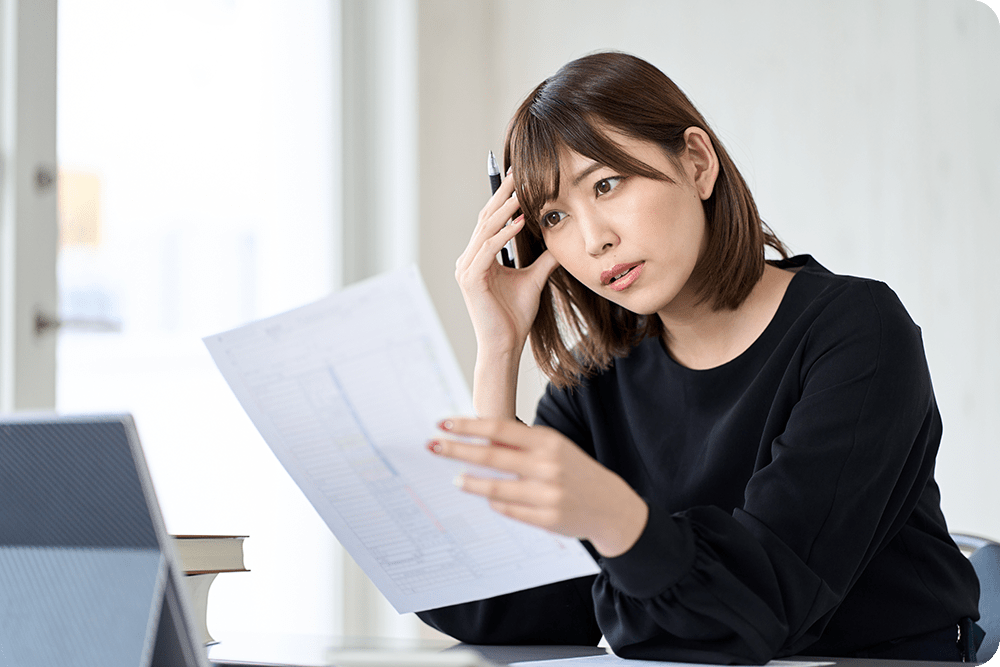
発注書に注文内容を手書きしてFAXで送る…。今も行われている注文方法ですが、毎日繰り返される受発注業務に使うのであれば、効率がよいとはいえません。
発注側は、毎回ほとんど同じ注文だとしても、都度手書きする手間がかかります。また、送ったFAXがかすれていて間違った注文になってしまったり、業務中に確認の連絡が入ったりすることもあるでしょう。
受注側からしても、届いたFAXを担当者に振り分けて、かすれなどで不明瞭な場合は電話などで得意先に確認しなくてはいけません。さらに、FAXの内容をパソコンに入力する手間もかかります。
手書きFAXによる注文は、誰でも簡単にできることこそメリットですが、毎日のように繰り返される業務としては、その効率の悪さがデメリットになります。
1-2.読み間違いや紛失などのミスが起こる
手書きFAXによる注文は、受注側の読み間違いが起こることがあります。受注側は、送られてきたFAXを見て、パソコンに手作業で入力していきますが、このとき、FAXがかすれていたり、字にクセがあったりすると間違えてしまうことがあるでしょう。
また、届いたFAXを担当者に振り分ける際、間違えて別の担当者の元に届けられてしまうこともあります。担当者の手元にFAXが届いても、他の書類に紛れて紛失してしまったり、うっかり違う場所に置いて処理を忘れてしまうといったヒューマンエラーが起こりやすいデメリットがあります。
1-3.受発注業務が属人化するリスクが高い
電話やFAXを使った受発注業務は属人化しがちです。例えば、到着確認の電話が毎度営業担当者宛にかかってくるケースや、FAXに書かれている内容が担当者しかわからないケースなど、心当たりがある方はいらっしゃるのではないでしょうか。
受発注業務が属人化するデメリットは、特定の担当者以外が対応できない状況になることです。担当者以外に業務がわからず、休暇中の担当者に連絡を入れることになったり、得意先が休暇中の担当者に直接連絡をとったりといったことが起こります。
また、担当者の異動や退職での引き継ぎにも時間がかかるようになり、配置転換がしづらくなるほか、人員が業務に固定されるため組織の柔軟性も損なわれます。こうした理由から、業務の属人化は避ける必要があるため、ルールを決めるなどの工夫が必要です。

2.FAX受発注を卒業する方法
2-1.FAX以外の方法は「電話」「メール」が一般的

FAX以外の受発注の方法としては「電話」や「電子メール」などがあります。
電話や電子メールで受注するメリットは、特別な機器がいらないことや、使い慣れている方法で発注ができることです。一方、電話の場合は受注の際に手を止めなくてはならず、聞き間違いが起こりやすいといったデメリットも存在します。
メールの場合、業務フローは電話に比べて改善されますが、メールで受信した内容を販売管理システムに打ち直す手間は解消できません。メールボックスに大量にメールが来る場合、受注確認を漏らす可能性も高くなり、FAXを使った受発注から大きく改善されるかは微妙なところです。
2-2.最もおすすめできる卒業の方法は「受発注システム」の導入
電話やFAX、メールなどでの受注に代わり、近年注目を集めているのが「受発注システム」です。
受発注システムは、発注側はインターネットに接続されたスマートフォンやパソコンなどを使い、専用のページから必要な商品を発注できるシステムで、受注側は注文内容をデータとして受けとることができます。そのため、電話やFAX、メールでの受注のように、手打ちでデータ化する必要がありません。
受注データをそのまま販売管理システムと連携できるものもあり、そうしたシステムを選べば、業務効率が飛躍的にアップすることが見込まれます。
3.受発注システムを導入するメリットとは?
3-1.受発注業務の負担が軽減でき業務に集中しやすくなる

受発注システムを導入することで、受発注業務にかかる負担を大幅に軽減できます。発注側は使い慣れたスマートフォンなどから、24時間いつでも発注が可能です。営業時間を気にして電話することや、発注書に手書きしてFAXを送る手間がなくなり、いつでも簡単に発注ができます。
受注側も、受発注システムに1本化することで、電話やFAX、メールなどバラバラに到着する発注内容をまとめる手間がなくなります。電話が集中したり、FAXが大量に届いたりといったことがなくなるため、より目の前の業務に集中しやすくなるでしょう。
こうした特長により、業務効率が改善され、より余裕を持って業務にあたれるようになります。その結果、残業時間の短縮も見込まれるでしょう。
3-2.ヒューマンエラーが減り正確性が向上する
電話による口頭での受発注は、聞き間違いや言い間違いが起こる可能性があります。また、FAXによる受発注の場合も、かすれによる読み間違いや、FAX用紙そのものを紛失してしまうことがありました。しかし、受発注システムを利用すれば、そのようなことはなくなります。
また、受発注システムでは、発注側が入力したデータが保存されるため、電話しながらとった注文内容のメモや、FAX用紙を紛失してしまい、受注を漏らしてしまうこともなくなります。受発注に関わるヒューマンエラーが減り、受発注業務の正確性が向上するでしょう。
3-3.情報の一元管理ができる
電話やFAX、メールなどバラバラな手段で受注している場合、それぞれ業務フローが異なっていました。また受注データも、従業員が電話で確認しながら手書きしたものや、FAXで届いた用紙、メールもあるため管理の手間は少なくありませんでした。
受発注システムを導入して受注経路を1本化すると、情報の一元管理が可能になります。受注内容はすべてシステム内のデータとして管理できるため、過去の受注データの検索も簡単にできるようになります。業務がシンプルになり、より少ない労力で受注管理ができるはずです。
3-4.ペーパーレス化・コスト削減が期待できる
受発注システムを導入し、受注経路をシステムに1本化することは、ペーパーレス化に寄与します。電話で注文を受けながらとっていたメモや、FAXで送られてきていた発注書がなくなるため、事業所がすっきりするでしょう。
受注した内容はデータ化されているため、紙を紛失するミスがなくなります。また、受信に使うFAX用紙も不要になるため、紙を購入するコストを削減できます。さらに、いらなくなった用紙をシュレッダーにかける手間や、専門の業者に溶解処理を依頼するコストも削減できます。
これまで受注用紙をファイリングして保管していた場合は、保管の手間や保管のためのスペースも不要になるため、保管場所の確保も不要になり、事務所が広く使えるようになるでしょう。
まとめ
手書きのFAX注文は、誰でも簡単にできる反面デメリットもあります。特に、受発注業務の効率化をする上では、ベストの方法とはいえないでしょう。
FAX以外の受発注の方法には、電話やメールなどがありますが、おすすめは受発注システムの導入です。業務の負担軽減、正確性の向上、情報の一元管理、ペーパーレス化とコスト削減などのメリットが期待でき、業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)を可能とします。
これを機会に受発注システムを導入し、受発注業務を効率化してみてはいかがでしょうか。
受発注業務の効率化にカシオの「BC受発注」
カシオのBC受発注は、受発注業務の効率化に最適です。得意先から発注が来るとメールや画面上のアラートでお知らせするので、うっかり忘れることがなくなり、内容を確認したら「受注取り込み」をクリックするだけで販売管理システムに発注データを自動連携できます。
電話やFAX、メールなどバラバラな手段で発注を受ける必要がなくなり、入力にかかる手間も大幅に削減できます。さらに、受注した後の入力ミスも起こらなくなるため、得意先からの信頼もアップするでしょう。
発注を行う得意先は、パソコンやタブレット、スマートフォンから専用ページにアクセスして発注すればよく、得意先ごとの商品マスタも用意できるため、操作は難しくありません。従来の発注方法からの切り替えをお願いしやすくするツールも揃っており、スムーズに受発注業務のDX化を進められるはずです。
以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://web.casio.jp/bc-order/
