
コラム

受発注業務とは?
受注・発注の意味や違い、一般的な流れを解説
2024.07.31|最終更新日:2024.07.31

企業活動において欠かせない「受発注業務」。しかし、その内容は意外と知られていないかもしれません。また、DX推進による業務効率化が求められる今、受発注システムの導入などによる受発注業務の改善も注目されています。
このコラムでは、受注と発注の違い、具体的な流れ、そして業務上の課題とその改善方法まで、受発注業務について詳しく解説します。業務効率化や得意先満足度向上を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
目次

1.受発注業務とは?
取引先から商品・製品の注文を受ける「受注」、その受注に応えるために仕入を行う「発注」。これら一連の業務をまとめて「受発注業務」と呼びます。まずは、受注業務と発注業務をそれぞれ説明します。
1-1.受注業務とは

受注業務は、得意先から商品・サービスなどの注文を受けて処理するプロセスのことです。
得意先から注文が入ったら、注文内容を確認して、販売管理システムなどへ入力します。そこから先は、仕入先への発注、倉庫への出荷指示など、業態によって様々です。また、企業によっては請求書の発行までを受注業務に含めているケースもあります。
受注業務を効率的に行うことで、納期に遅れたり、在庫を抱えすぎたりといったことが減らせます。収益の最大化のために欠かせない重要な業務と言えるでしょう。
1-2.発注業務とは
発注業務とは、自社の商品やサービスの販売にあたって必要なモノを仕入先に発注する業務です。
自身の得意先と約束した期日に間に合うよう、モノの数量や納期を指定します。このとき、在庫量を正確に把握し、在庫の過剰や不足が起こらないようにすることも大切です。
発注業務を正確に行うことで、過剰在庫で会社の財政を圧迫したり、在庫不足で機会損失を起こしたりすることを減らせます。受注業務と同様、重要度の高い業務です。
1-3.受注と発注の違い
ここまで説明したように、受注と発注は深く関連しています。しかし、業務としては異なります。
- 受注業務:得意先から自社の商品・サービスの注文を受ける
- 発注業務:自社の商品・サービスの販売に必要なモノを仕入先に注文する
ビジネスにおいて受注とは、得意先から自社の商品・サービスの注文を受けることです。発注は、得意先に商品・サービスを仕入れるために必要なモノを仕入先に注文することです。
ビジネスの現場では、注文する側、注文される側がそれぞれ受注・発注という言葉を使います。そのため、少々わかりづらい部分があるかもしれません。

2.受発注業務のフロー
続いて、受発注業務の具体的なフローを説明します。ここでは、発注側と受注側双方の動きをみていきましょう。
2-1.見積もり

発注側
発注者が受注者(となる企業・事業者)に対し、商品やサービスを購入するための見積もりを依頼します。
BtoB(法人間取引)では、発注の時期や量によって価格が変動することが多く、都度見積もりを行うことが多くなっています。
見積書には、品物と数量、価格、支払条件、そして納期などが記載されます。発注者は必要に応じて相見積もりを行って比較・検討すると同時に、社内の予算を確保・申請します。
受注側
受注者は、発注者からの見積依頼に応じ、取引内容や金額、納期などを検討し見積書を作成します。
発注者が他社との相見積もりをとっている場合、納期や金額の交渉が必要になる場合があります。その際は、複数回見積もりを行うことになるでしょう。
2-2.発注の確定(契約の締結)
発注側
発注者は見積もりの内容を確認し、金額・納期などの条件に納得できたら発注を行います。
発注先を決定したら、注文書・発注書を送付します。発注先からの確認の連絡や、注文請書を受け取った時点で契約が成立し、商品やサービスの提供準備が始まります。
受注側
発注者から注文があり、注文書・発注書を受け取ったら、それを受けて折り返しの連絡、もしくは注文請書を送付して契約を成立させます。
発注者の情報を販売管理システムなどに入力して、必要に応じて受注伝票の作成も行うのもこのタイミングです。
商品・サービスを納品するために仕入が必要な場合は、今度は自らが発注者となり取引先から商品の購入(仕入)を行います。
2-3.商品発送・受領
受注側
受注した商品・サービスが期限までに納められるよう、仕入や出荷を行います。必要に応じて、納品書・出荷指示書を発行します。
出荷に際しては検品と梱包を行います。商品の品質を確保し、安全に輸送するために必要な作業です。
発注側
発注した商品・サービスを受け取り、注文通りに納品されたことを確認します。必要に応じて、自社内で在庫管理を行います。
2-4.請求・支払い
受注側
商品を出荷したら、請求書を作成し発注者に渡します。契約時に決定した期日を支払い期限とし、入金を待ちます。
発注者からの入金があったら、証明書として領収書を発行して発注者に渡します。以上で取引完了です。
発注側
商品が納品されると請求書が届きます。そこに書かれた期日に従って、受注者に対し支払いを行います。
支払いを行うと領収書が送られてくるので保管します。以上で取引完了です。
3.受発注業務の課題・改善方法
受発注業務には、いくつかの課題があります。その改善方法も含めて解説します。
3-1.【課題】業務が煩雑になりがちでミスも起こりやすい
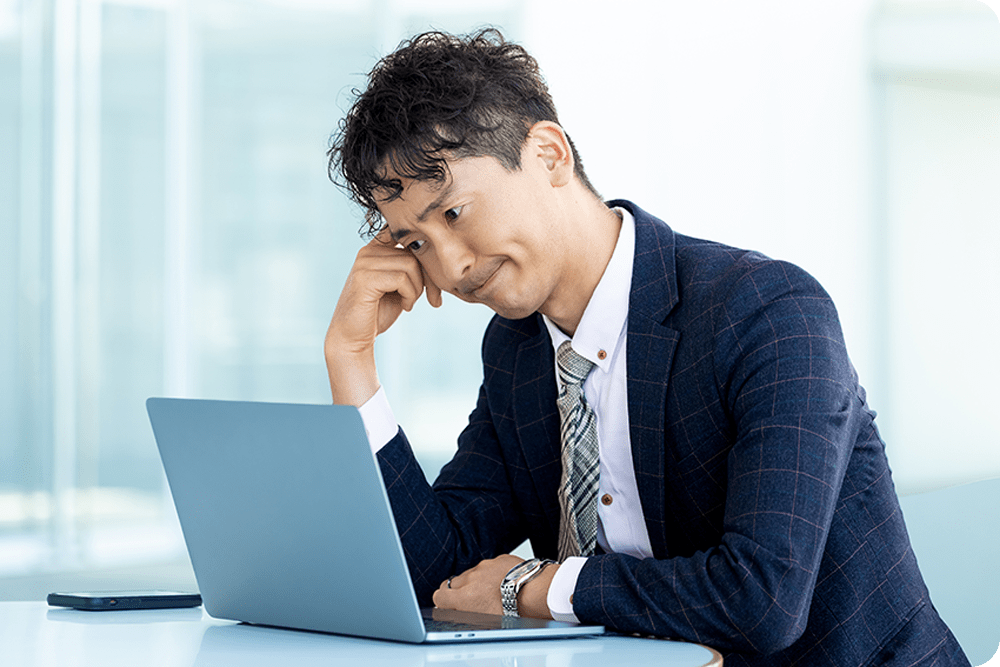
受発注業務では、商品の情報、得意先ごとの契約条件などの取引データを正確に管理することが重要です。これらが絡み合い、かつ件数が多いと業務が複雑になります。そうすると、注文の取り違えや、請求書の誤り、在庫の不整合を起こすことがあり、ミスが起こりかねません。
また、IT化が進んでいないケースでは、手作業によるデータ入力や伝票管理が行われ、これもミスの原因になります。また、受発注業務は少人数で対応することが多く、注文や発注件数が多い日は担当者に負担が集中しがちです。そうすると業務効率が低下し、ミスも起こりやすくなるでしょう。
3-2.【改善方法】業務フローの整理と受発注システムの導入
受発注業務を改善するには、業務フローを整理することが大切です。また、受発注システムの導入も効果的と考えられます。
まずは、業務プロセスを「見える化」します。フローチャートなどを用いることで、各業務で行うことが明確になり、無駄な作業や遅延が減少することでしょう。さらに、エラーやミスの早期発見がしやすくなるはずです。こうした改善により、新人スタッフのトレーニングや業務の共有もスムーズに行えるようになるでしょう。
受発注システムは、受発注業務を自動化するための専用システムです。得意先からの受注をシステムで受け付けられるため、定期的な受注のある得意先とのやりとりをスムーズにできます。
受付から納品、請求までの一連のステップを半自動的に管理できるため、電話やFAX対応の手間を減らすことができ、伝票の打ち間違いなどのヒューマンエラーも減らせます。また、他部署とリアルタイムで情報共有可能となるため、受発注業務全体が「見える化」され、業務の属人化も防げます。
3-3.【改善するメリット】ミスの抑制・コスト削減・得意先満足度向上
受発注業務の改善は、業務効率化やコスト削減だけでなく、得意先満足度向上にもつながるなど、企業にとって多くのメリットがあります。
ミスの抑制
業務フローの整理と受発注システムの導入により、人為的なミスを大幅に減らすことができます。受注内容の取り違えや、請求書の誤り、在庫の不整合などが起こりにくくなることで、企業の信頼性を損なうリスクを軽減できるでしょう。
コスト削減
受発注業務に専用システムを導入することで、電話やFAXなどで行っていた受注をシステムに一本化できます。これにより、事務処理にかかる労力を削減し、人的コストを削減できます。
得意先満足度向上
受発注業務がスムーズに行われることで、ミスのない正確な納品につながり、得意先満足度を高めることができるでしょう。また迅速かつ正確な対応は、得意先からの信頼を獲得し、長期的な関係構築にも役立つでしょう。
まとめ
受発注業務は、企業の円滑な運営に欠かせない重要な業務です。受注から発注、そして納品・請求までの一連の流れを理解し、それぞれのステップで発生しうる課題を把握しておくことが大切になります。
業務フローの整理や受発注システムの導入など改善策を講じることで、業務効率化やコスト削減、得意先満足度向上を実現できるはずです。このコラムが受発注業務の改善の一助となれば幸いです。
受発注業務の効率化にカシオの「BC受発注」
カシオのBC受発注は、受発注業務の効率化に最適です。得意先から発注が来るとメールや画面上のアラートでお知らせするので、うっかり忘れることがなくなり、内容を確認したら「受注取り込み」をクリックするだけで販売管理システムに発注データを自動連携できます。
電話やFAX、メールなどバラバラな手段で発注を受ける必要がなくなり、入力にかかる手間も大幅に削減できます。さらに、受注した後の入力ミスも起こらなくなるため、得意先からの信頼もアップするでしょう。
発注を行う得意先は、パソコンやタブレット、スマートフォンから専用ページにアクセスして発注すればよく、得意先ごとの商品マスタも用意できるため、操作は難しくありません。従来の発注方法からの切り替えをお願いしやすくするツールも揃っており、スムーズに受発注業務のDX化を進められるはずです。
以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://web.casio.jp/bc-order/
