
コラム

「帳合」とは?
小売業における帳合取引の意味を徹底解説
2024.08.30|最終更新日:2024.08.30

「帳合」という言葉をご存知でしょうか?会計用語としての意味もありますが、小売業においては「帳合取引」としての意味で使われている言葉です。
本記事では、帳合取引の具体的な内容や、取引に伴うメリットやリスクなど、帳合取引がなぜ流通において重要なのかを詳しく解説します。小売業における「帳合」への理解が深まれば幸いです。
目次

1.帳合とは?
帳合とは、会計用語で「手元にある現金・商品の勘定と帳簿を照合する作業」のことを指す言葉です。
しかし、小売業や卸売業では「取引関係がある」ことを示す言葉として使われます。
1-1.会計用語の「帳合」
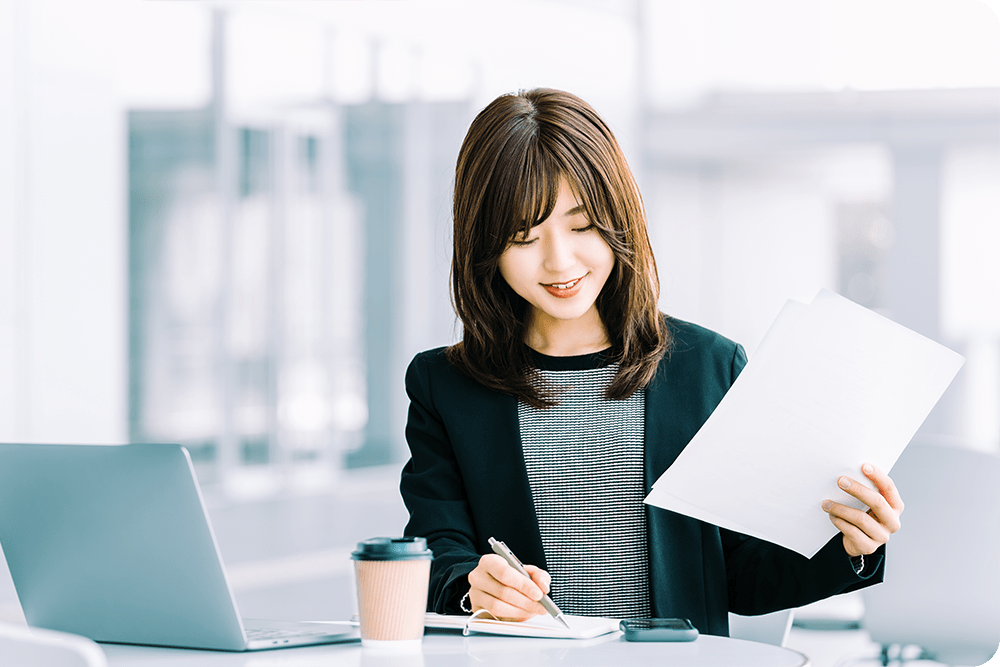
会計用語の「帳合」は「帳簿合わせ」とも呼ばれ、手元にある現金・商品の勘定と帳簿を照合する作業のことを指しています。
帳合の目的は、帳簿に記載されている金額や数量が正しいかを確認することで、定期的に整合性を確認して帳簿の正確性を高める目的で行われます。
1-2.卸売業や小売業における「帳合」
小売・卸売業界での帳合については、「帳合取引」と「帳合先」という2つの用語を通して解説します。
帳合取引
小売・卸売業界では、一般的に「帳合取引」を略して「帳合」と呼びます。
この場合の「帳合」は、「Aという商品を、Bという卸売業者を通して販売することが決まっている状態」を表す言葉です。
言い換えれば、その商品を流通させるための独占的な契約のことで、商品を円滑に流通させるために重要なものとなっています。
帳合先
帳合取引における「帳合先」とは、メーカーや小売業者から見た「卸売業者」のことです。メーカーの製品を販売する卸売業者は「ベンダー」とも呼ばれます。
先ほど例に挙げた、「Aという商品を、Bという卸売業者を通して販売することが決まっている状態」の場合、「商品Aの帳合先は卸売業者B」といった表現をします。

2.帳合取引が行われる理由
帳合取引はどのような理由から行われるのでしょうか。そこには、日本ならではの事情も関係しています。
2-1.卸売業者に任せることで流通が円滑になるため

日本は諸外国と比べて商品数が多く、しかも小ロットでの注文が多くなりがちな特徴があります。しかも、平野が少なく山間部が多いため、集落にまで流通させるのが大変です。
こういった難しい地形の中で、効率よく商品を流通させるには、それぞれの地域に精通している卸売業者の力が不可欠と言えます。そのため、卸売業者がメーカーと小売業者の間に入り、流通させるスタイルが確立されました。
現在は物流が発達し、メーカーが直接販売することも非効率ではなくなりました。しかし、特に地方では小売業者と卸売業者の関係が非常に強固です。そのため、メーカーも卸売業者に任せたほうが基本的にスムーズと考え、現在も帳合取引が主流となっています。
2-2.信用ある業者と安定した取引をするため
小売業者は、日々安定して商品の供給がされなければ品揃えを確保できません。そのため、実績があり信用できる卸売業者との取引が非常に重要となります。
また、流通業界では掛け売り(後払い)が主流となるため、卸売業者側も信用できる小売業者と取引をしたい事情があります。
さらに、このような取引体制は、メーカーが新規取引先の開拓や信用調査にかかるコストを削減できるメリットもあります。このように、信用できる業者間の帳合取引は、メーカー、小売業者、卸売業者の3者にそれぞれメリットがあるのです。
3.帳合取引のメリット・デメリット
帳合取引には、流通の円滑性や、信用の問題以外にもいくつかのメリットがあります。メーカー、小売業者それぞれのメリットを解説します。
3-1.メーカーにとっての帳合取引のメリット

メーカーが帳合取引をするメリットは主に3つあります。
- 販売コストが削減できる
- エンドユーザーの情報を収集しやすい
- 知名度の低い商品・メーカーでも流通させやすい
販売コストが削減できる
帳合取引では、商品の「受注・販売・流通」を帳合先である卸売業者に任せることができます。メーカーは、この工程にかかる労力を丸ごと削減できるため、コスト削減が可能になります。
特に、メーカー自ら販売先を選定し契約を結ぶ作業は煩雑で、多くの人員も必要とします。また、メーカー自ら販売する場合は、日本の隅々にまで流通させるための物流コストも必要になります。
エンドユーザーの情報を収集しやすい
帳合先の卸売業者から、販売状況やエンドユーザーの声など、小売業者からの情報を収集することもできます。収集した情報は、生産量の決定や製品の開発に役立つため、非常に重要です。
メーカーの営業部署でも情報は収集できますが、情報収集には労力とコストがかかります。また、長年親密な関係を築いてきた、卸売業者と小売業者の間だからこそわかることもあると考えられます。
知名度の低い商品・メーカーでも流通させやすい
帳合取引では、商品やメーカーの知名度が低くても流通させられるメリットがあります。
メーカーが自ら小売業者に販売する場合、知名度の低い商品やメーカーは扱ってもらえるチャンスが少なくなってしまいます。それが良い商品でも、販路を確保できなければ収益は確保できません。
しかし、信用できる卸売業者からの紹介であれば、知名度の低い商品を取り扱ってもらえる可能性が高まります。特に、中小規模のメーカーにとっては大きなメリットとなるはずです。
3-2.小売業者にとっての帳合取引のメリット
小売業者が帳合取引をするメリットは主に3つあります。
- 仕入の労力を減らせる
- 自社単独では難しい商品も仕入れられる
- 業界の情報を収集しやすい
仕入の労力を減らせる
小売業者は、卸売業者と帳合取引をすることで、メーカーと直接取り引きをする労力がなくなります。卸売業者が取り扱っている商品であれば、初めて取引するメーカーの商品もスムーズな仕入が可能です。
また、卸売業者の多くは在庫状況も把握しています。そのため、発注しすぎや発注漏れなどのリスクも低くなります。
自社単独では難しい商品も仕入れられる
まだ事業が小さい小売業者が、これまで取引がないメーカーの商品を仕入れようとしたとき、信用の問題から直接契約が難しいことがあります。
しかし、そんなときでも間に卸売業者が入れば、卸売業者の信用で商品の仕入が可能です。卸売業者を経由することで仕入れられる商品の幅が広がることも、帳合取引のメリットと言えます。
業界の情報を収集しやすい
卸売業者は、小売業者の同業他社を含めたマーケットの情報を持っています。業界について幅広く情報を持っている商社などがその筆頭と言えるでしょう。
卸売業者は小売業者単独では得られない情報を持っているため、そういった情報を入手することで、マーケットの動向などがわかり、自社の事業の参考になることでしょう。
3-3.帳合取引のデメリット
帳合取引にはデメリットもあります。主に次の3つです。
- 価格を安くしづらい
- コスト高になる場合がある
- 独占禁止法に抵触する場合がある
価格を安くしづらい
帳合取引では、間に卸売業者が入ることもあり、メーカーの小売希望価格より低い金額での販売が難しくなります。
利益を生み出すためには販売価格を高くする必要があるため、価格を安くしづらくなります。
コスト高になる場合がある
小売業者と卸売業者の信頼関係は、商品の安定した仕入のためにも重要なものです。
しかし、小売業者が特定の卸売業者のみに依存する状態となり、卸売業者の言い値で取引する状況が続くと、仕入にかかるコストが高くなってしまいます。
そうすると、価格競争力が失われ、販売面で不利となることが考えられます。
独占禁止法に抵触する場合がある
帳合先との関係が強すぎて、取引が1つの業者に限定されると、他業者の市場参入を阻止していると判断されて独占禁止法に抵触する場合があります。
他業者から公正取引委員会へ相談されたことから、調査対象となることが考えられるため、特にメーカーや大規模小売業者は十分なリスク管理が必要です。
まとめ
帳合取引は、日本の小売業界で長年にわたり重要な役割を果たしてきた取引形態です。メーカー、卸売業者、小売業者の三者間の信頼関係により、効率的な商品流通を実現する一方で、価格のコスト増加や独占禁止法への抵触リスクなどの課題も抱えています。
帳合取引を利用する際は、そのメリットとデメリットを十分に理解し、デメリットを最小限に抑える工夫をすることが重要になるでしょう。
受発注業務の効率化にカシオの「BC受発注」
カシオのBC受発注は、受発注業務の効率化に最適です。得意先から発注が来るとメールや画面上のアラートでお知らせするので、うっかり忘れることがなくなり、内容を確認したら「受注取り込み」をクリックするだけで販売管理システムに発注データを自動連携できます。
電話やFAX、メールなどバラバラな手段で発注を受ける必要がなくなり、入力にかかる手間も大幅に削減できます。さらに、受注した後の入力ミスも起こらなくなるため、得意先からの信頼もアップするでしょう。
発注を行う得意先は、パソコンやタブレット、スマートフォンから専用ページにアクセスして発注すればよく、得意先ごとの商品マスタも用意できるため、操作は難しくありません。従来の発注方法からの切り替えをお願いしやすくするツールも揃っており、スムーズに受発注業務のDX化を進められるはずです。
以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://web.casio.jp/bc-order/
