
コラム

「借入金」とはどんな勘定科目?
種類や仕訳まで解説
2024.09.30|最終更新日:2024.09.30
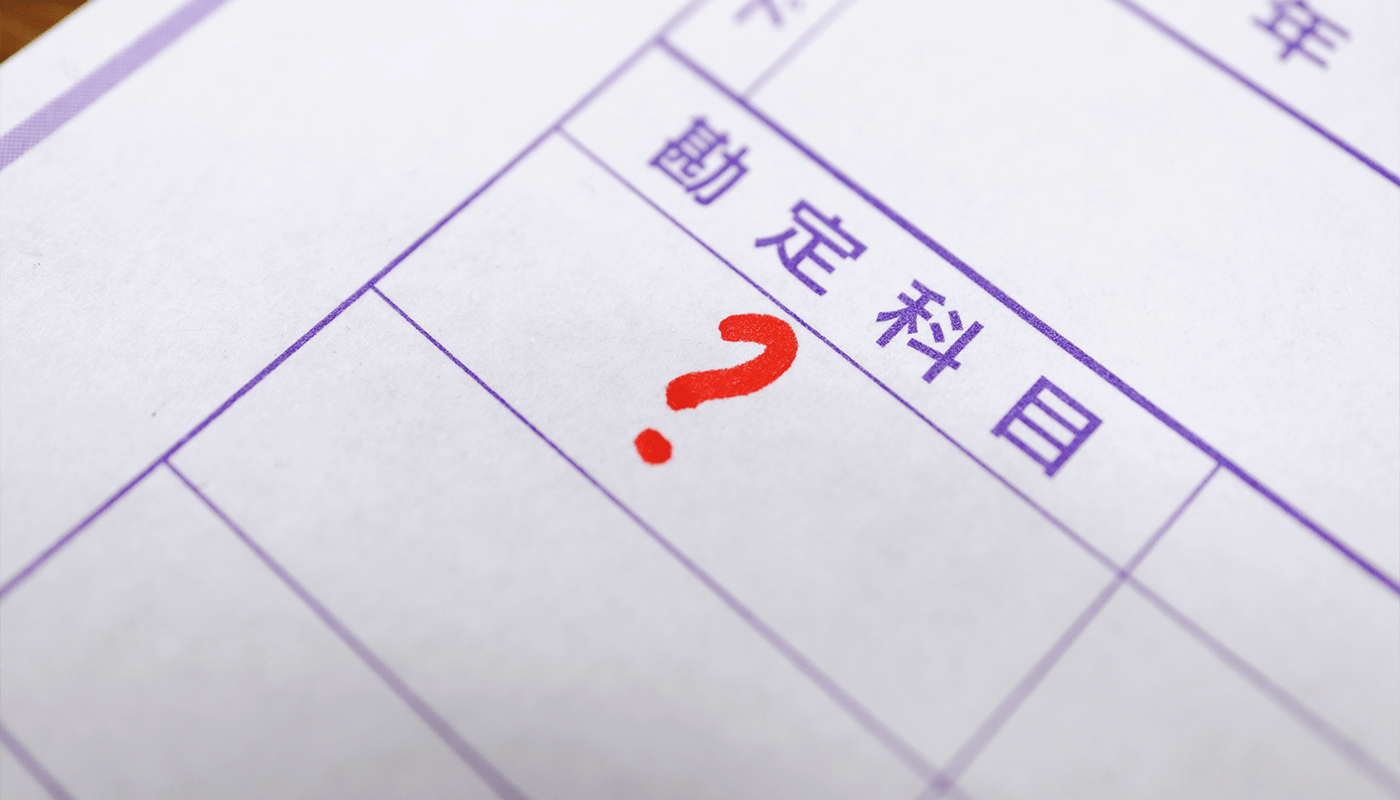
借入金は企業経営において重要な資金調達手段の一つです。しかし、その仕組みや会計処理、メリットとリスクを正しく理解していないと、経営に支障をきたす可能性があります。
このコラムでは、借入金の基本的な概念から種類、勘定科目、仕訳方法、メリットやリスクまで詳しく解説します。経営者や経理担当者にとって有益な情報となるはずです。
目次

1.借入金(かりいれきん)とは?
借入金(かりいれきん)とは、借りたお金のことです。対義語は「貸付金(かしつけきん)」となります。
個人、金融機関から借りた場合、取引先企業から融資を受ける場合、これらすべてが「借入金」として扱われます。また、企業が借用証書や約束手形を差し入れて借りるお金も含まれます。
企業が事業を続けるため、または拡大するために、金融機関からお金を借りる(融資を受ける)ことは一般的です。なお、借入金には通常、利息が発生します。
1-1.借入金の種類

借入金には種類があり、それぞれ会計処理の方法が異なります。金融機関からの借入金は、次の4種類です。
| 借入金の種類 | 概要 |
|---|---|
| 証書貸付 | 借手が貸手と金銭貸借契約を結び、金銭消費貸借契約証書を差し入れて借り入れを行う。「借入金」は一般的にこれを指す。不動産が担保となる場合もある。 |
| 手形貸付 | 金融機関に約束手形を振り出し融資を受ける。担保なしでの短期融資を希望する場合に用いられることが多い。 |
| 手形割引 | 他社が振り出した期日前の手形を、金融機関などに買い取ってもらうことで融資を受ける。額面金額から手数料が差し引かれる。 |
| 当座借越 | あらかじめ設定した限度額までなら、自由に融資を受けられ、返済できる方法。金融機関の審査が厳しい。 |

2.借入金の勘定科目
借入金に関して会計処理を行うときは、「長期借入金」と「短期借入金」、そして「支払利息」を使います。
2-1.長期借入金・短期借入金
借入金は、借入期間が1年超か1年以内かによって「長期借入金」と「短期借入金」に分類されます。
厳密には、同じ融資であっても、1年超で返済する部分と1年以内に返済する部分に分けて処理を行います。
| 借入金の種類 | 概要 |
|---|---|
| 長期借入金 | • 借入期間1年超 • 貸借対照表上では「固定負債」 • 固定資産の購入などに利用される • 主に証書貸付で調達される |
| 短期借入金 | • 借入期間が1年以内 • 貸借対照表上では「流動負債」 • 運転資金などに利用される • 主に手形貸付や当座借越で調達される |
2-2.支払利息
借入金に利息が生じた場合は、「支払利息」で仕訳します。
支払利息は、借入金やローンにかかる利子のことです。借り入れ直後など、利息だけ支払う間は、支払利息のみを計上することになります。
3.借入金の仕訳例
ここでは、借入金の勘定科目と、具体的な仕訳例を見ていきます。
3-1.【例1】借入金が入金されたとき
例:銀行から100万円の融資を受け、普通預金口座に入金された。内、1年以内に返済期日が来る30万円を短期借入金とし、残りの70万円は長期借入金として計上する。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 100万円 | 短期借入金 | 30万円 |
| - | - | 長期借入金 | 70万円 |
3-2.【例2】利息を支払ったとき
例:借入後3か月は利息のみの支払いで、その利息1万円を支払った。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 支払利息 | 1万円 | 普通預金 | 1万円 |
3-3.【例3】借入金を返済したとき
例:借入金の元本100万円と利息1万円を普通預金から返済した。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 100万円 | 普通預金 | 101万円 |
| 支払利息 | 1万円 | - | - |
3-4.【例4】決算時
例:来年返済する分を長期借入金から短期借入金に振り替えた。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 100万円 | 短期借入金 | 100万円 |
4.借入金のメリットとリスク
借入金には、メリットとリスクがあります。それぞれを詳しくみてみましょう。
4-1.借入金のメリット

借入金は「借金」ですから、返済義務があり利息も発生します。そのため、無借金経営が良いと考える経営者は多いかもしれません。しかし、次のようなメリットがあります。
- 金融機関との関係を強化できる
- 事業資金に余裕ができる
- 将来の事業に投資できる
金融機関との関係を強化できる
一つ目のメリットは金融機関との関係強化です。これを痛感するのは、大きな資金調達が必要になったときでしょう。無借金経営を続けていて、金融機関とのお付き合いがない場合、すぐに大きな融資を受けることは基本的にできないと考えましょう。
そのため、あえて小さな融資を受け、確実に返済することを繰り返し、金融機関との信頼関係を構築する経営者もいます。いずれ、大きな資金調達が必要になったときに備えるために、大切な考え方です。
事業資金に余裕ができる
事業を続けていく中で、取引先の倒産などで入金がストップしてしまうことがあるかもしれません。そんな場合、事業資金に余裕がなくなると、支払いが滞り、自社の信頼に悪影響を与えかねません。
そんなとき、短期的にでも事業資金を借り入れることで、事業資金に余裕ができ、信頼に傷をつけずにすみます。それと同時に、確実に返済することで、金融機関との関係も強化できるのです。
将来の事業に投資できる
新製品の研究・開発を行う場合や、新しい機械を導入する場合、変化する社会に対応する場合など、まとまった資金が必要になることがあります。そんなとき、長期的な借り入れを行うことで、自社の将来に投資ができます。
仮に、借り入れを行わずに自己資金だけを投資に使う場合、自己資金の範囲での投資となり、その予算規模によっては競争力を徐々に失うこともあります。しかし、適切な計画のもとで借り入れを行い事業に投資をすれば、それ以上のリターンを見込めるでしょう。
4-2.借入金のリスク
借入金は、返済しなくてはいけません。しかも、利息が発生します。さらに、基本的に毎月返済が必要です。
借入金が増えすぎてしまうと、返済できなくなります。そうして資金がショートすると、返済が滞ることで金融機関からの信用を失い、支払いが滞ることで取引先からの信用も失うでしょう。その先に待っているのは倒産です。これが借入金のリスクと言えます。
お金を借りれば事業が回ると安易に考えるのではなく、借り入れをしなくても問題ないほどの健全な経営を行いながら、「計画的に」「敢えて」借り入れを行う姿勢が大切です。
まとめ
借入金の基本概念からその種類、会計処理の具体例、そして実際に企業が直面するメリットおよびリスクまで、幅広い視点から解説してきました。
借入金には、「証書貸付」や「手形貸付」など、さまざまな形態があり、それぞれの特性に応じた会計処理方法が求められます。ここで紹介したことが、適切な会計処理の手助けになれば幸いです。
受発注業務の効率化にカシオの「BC受発注」
カシオのBC受発注は、受発注業務の効率化に最適です。得意先から発注が来るとメールや画面上のアラートでお知らせするので、うっかり忘れることがなくなり、内容を確認したら「受注取り込み」をクリックするだけで販売管理システムに発注データを自動連携できます。
電話やFAX、メールなどバラバラな手段で発注を受ける必要がなくなり、入力にかかる手間も大幅に削減できます。さらに、受注した後の入力ミスも起こらなくなるため、得意先からの信頼もアップするでしょう。
発注を行う得意先は、パソコンやタブレット、スマートフォンから専用ページにアクセスして発注すればよく、得意先ごとの商品マスタも用意できるため、操作は難しくありません。従来の発注方法からの切り替えをお願いしやすくするツールも揃っており、スムーズに受発注業務のDX化を進められるはずです。
以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://web.casio.jp/bc-order/
