
コラム

「印紙税法」とは?
収入印紙が必要になる課税文書と税額をご紹介
2024.09.30|最終更新日:2024.09.30

契約書や手形など、ビジネスで頻繁に作成される文書の多くに「印紙税」が課されます。印紙税は「印紙税法」に基づいて徴収される税金で、印紙税法では、税額や納税方法、未納の場合の罰則などを規定しています。
本コラムでは、印紙税法の概要や、主な課税文書とその税額、さらに印紙税に関するよくある疑問についてわかりやすく解説します。適切な税務処理のために、ぜひ参考にしてください。
目次

1.印紙税法とは?
印紙税法とは、印紙税の対象となる文書を定めた法律です。印紙の貼り付けが義務付けられる「課税文書」や、納税の義務を負う対象者、印紙税額、納税方法、そして印紙税を納付しなかった場合の罰則などが定められています。
印紙税法上、納税の義務を負うのは課税文書の作成者です。共同で作成した場合は、連帯して納税の義務が発生します。納税は印紙を貼り付けることで行われますが、一部例外として金銭で納付することもあります。

2.印紙税が必要になる「課税文書」と「税額」
ここからは、印紙税の貼付が必要な「課税文書」について、企業の経営に関係が深い、代表的なものをピックアップして見ていきます。
なお、課税文書には「1号文書」から「20号文書」まであり、それぞれ印紙税額が異なります。
2-1.第1号文書
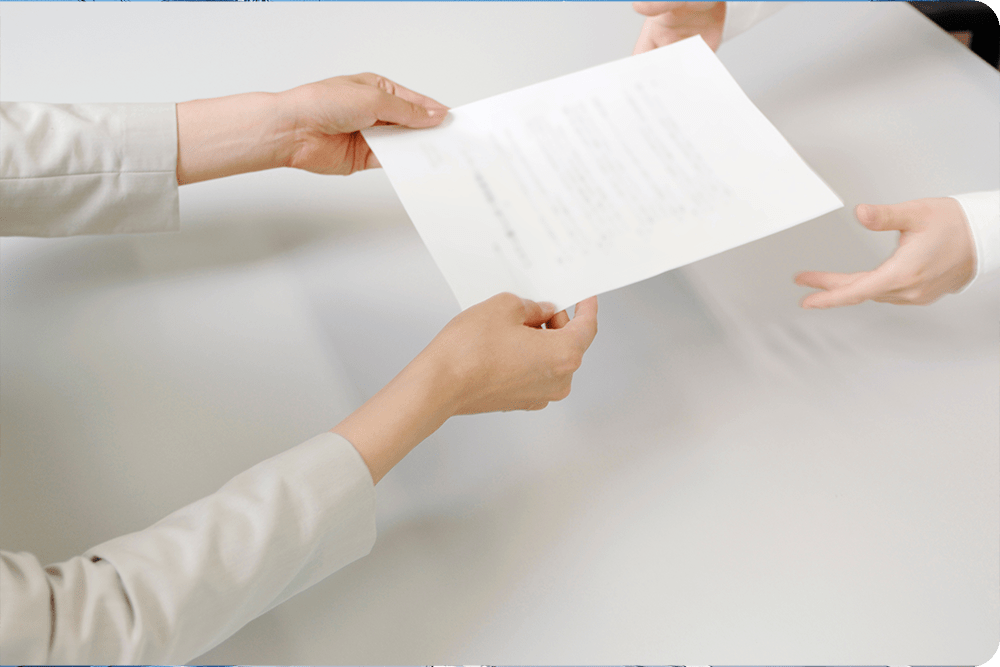
第1号文書に該当するのは以下の4つです。
- 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
- 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
- 消費貸借に関する契約書
- 運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)
税額は次のように定められています。
| 記載された金額 | 税額 |
|---|---|
| 1万円未満(※) | 非課税 |
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
※第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
出典:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
2-2.第2号文書
第2号文書に該当するのは、「請負に関する契約書」です。
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書などが該当します。
税額は次のように定められています。
| 記載された金額 | 税額 |
|---|---|
| 1万円未満(※) | 非課税 |
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
※第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
出典:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
2-3.第3号文書
第3号文書に該当するのは「約束手形または為替手形」です。
税額は次のように定められています。
| 記載された金額 | 税額 |
|---|---|
| 10万円未満 | 非課税 |
| 10万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
出典:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
2-4.第4号文書
第4号文書に該当するのは「株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券」です。
税額は次のように定められています。
| 記載された金額 | 税額 |
|---|---|
| 500万円以下 | 200円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2千円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 1万円 |
| 1億円を超えるもの | 2万円 |
2-5.第5号文書
第5号文書に該当するのは「合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書」です。
印紙税額は一律で1通または1冊につき「4万円」となっています。
2-6.第7号文書
第7号文書に該当するのは「継続的取引の基本となる契約書」です。
印紙税額は一律で1通または1冊につき「4千円」となっています。
なお、契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは対象外となります。
2-7.その他の課税文書
これまで紹介した以外にも、次のような文章が課税文書に該当します。
• 預金証書、貯金証書
• 保険証券
• 信用状
• 配当金領収証、配当金振込通知書
• 売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
• 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
• 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
• 判取帳
3.印紙税法に関するQ&A
ここでは、印紙税法に関してよくある疑問をまとめました。
3-1.印紙税の対象かを確認する方法は?
その文書が、印紙税の対象かを確認するもっとも確実な方法は、国税庁のホームページを確認することです。
以下の2つのページと、資料で確認できます。
文書の種類、印紙税額、非課税文書になる要件、その他注意事項が記載されているため、こちらで確認し、必要に応じて収入印紙を用意しましょう。
3-2.印紙を貼り付け忘れるとどうなる?
課税文書に印紙を貼り付けなかった場合の対応について、国税庁では次のように回答しています。
出典:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁
また、印紙税法第5章(第21条~24条)では、「偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者」に対して、「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」を定めています。
出典:印紙税法 第5章(第21条~24条)|e-GOV 法令検索
印紙税の対象となるか、金額は間違えていないかをしっかり確認し、適切に印紙税を納付するよう、十分に注意しましょう。
3-3.電子契約書(電子書面)にも印紙税はかかる?
国税庁では、電子契約の場合、収入印紙は不要としています。
これは、印紙税法上で規定している「課税文書の作成」はあくまで紙媒体を想定しており、電子契約メールや電子契約サービスを利用する場合、これに当たらないと考えられるためです。
ただし、電子契約した後に、紙でもやりとりした場合は印紙税の対象となるため注意が必要です。
出典:印紙税法 第1章(第2条~3条)|e-GOV 法令検索
出典:文書回答事例|国税庁
4.まとめ
印紙税法では、課税対象となる文書や税額を詳細に定めており、そこには、契約書や手形など、ビジネスで日常的に使用される文書も多く含まれています。
印紙税の納付を怠ると、罰則の対象となる可能性があるため、自社で作成する文書が課税対象かどうか、そして適切な税額はいくらかを常に確認する必要があります。
一方、電子契約書は原則として課税対象外となるなど、デジタル化に伴う変化もあります。印紙税法を正しく理解し、事業活動を円滑に進めるための参考にしていただければ幸いです。
受発注業務の効率化にカシオの「BC受発注」
カシオのBC受発注は、受発注業務の効率化に最適です。得意先から発注が来るとメールや画面上のアラートでお知らせするので、うっかり忘れることがなくなり、内容を確認したら「受注取り込み」をクリックするだけで販売管理システムに発注データを自動連携できます。
電話やFAX、メールなどバラバラな手段で発注を受ける必要がなくなり、入力にかかる手間も大幅に削減できます。さらに、受注した後の入力ミスも起こらなくなるため、得意先からの信頼もアップするでしょう。
発注を行う得意先は、パソコンやタブレット、スマートフォンから専用ページにアクセスして発注すればよく、得意先ごとの商品マスタも用意できるため、操作は難しくありません。従来の発注方法からの切り替えをお願いしやすくするツールも揃っており、スムーズに受発注業務のDX化を進められるはずです。
以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://web.casio.jp/bc-order/
