
コラム

「減損損失」とは?
概要・目的・判定の流れなどを解説
2024.10.24|最終更新日:2024.10.31
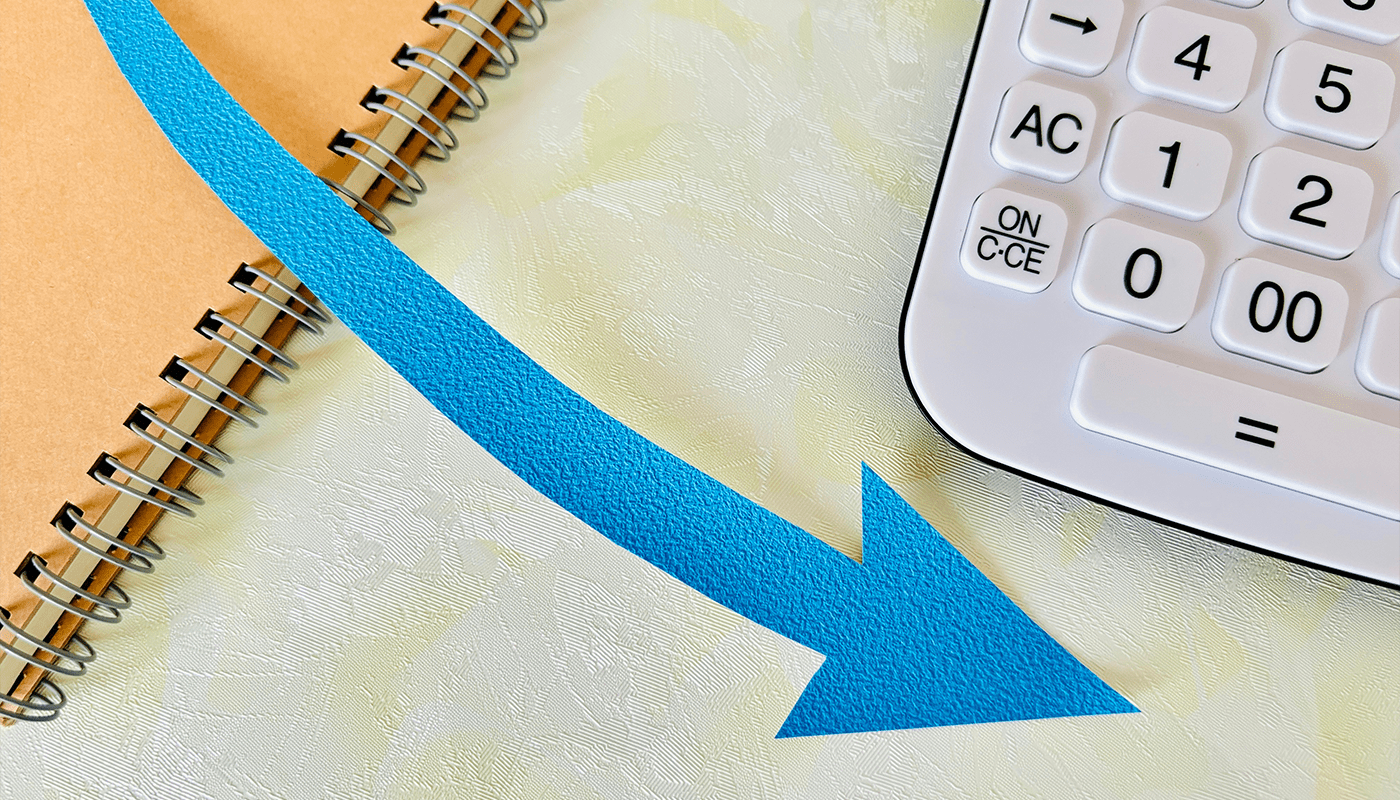
減損損失とは、企業が保有する固定資産などの投資額が、将来的に回収できないと見込まれる場合に計上される損失のことです。減損損失は、財務諸表において実態を正確に示すために不可欠な処理と言えます。
ここでは、減損損失の概念や目的、対象となる資産、判定方法、そしてその影響について詳しく解説します。
目次

1.減損損失とは?概要を解説
減損損失とはどのようなものでしょうか。概要や目的などを解説します。
1-1.「減損損失」は減損会計で用いる勘定科目

過去に投資した資産の資産価値を切り下げ、損益計算書に反映させる会計処理を「減損会計」と言います。減損会計は、投資に見合った金額を回収できないときに行われるもので、下落した価値は損失として扱われます。
そして、この損失を示す勘定科目が「減損損失」です。財務諸表では、原則、損益計算書の特別損失として扱われます。
なお、減損会計は上場企業や大企業では義務付けられていますが、中小企業には義務がありません。
1-2.減損損失の対象となる3つの固定資産
減損損失の対象となる資産は次の3つです。
- 有形固定資産(土地、建物など)
- 無形固定資産(借地権、商標権など)
- 投資その他の資産(株式配当、預金利息など)
「有形固定資産」は、営業活動において長期間使用する目的で所有している資産のことです。具体的には、土地や建物、製造用機械や車両などが該当します。
「無形固定資産」は、1年を超えて利用される、物理的な形態がない資産のことです。具体的には、借地権、商標権などの権利、ソフトウェアなどが該当します。
「投資その他の資産」は、有形固定資産、無形固定資産のどちらにも該当しない資産です。例えば、株式配当や預金利息などが該当します。
なお、次のようなケースは他の会計基準が適用されることから、減損会計の対象になりません。
- 販売目的のソフトウェア
- 投資有価証券などの金融資産
- 前払年金費用
1-3.減損会計を行う目的・理由
固定資産は、使用することで年々価値が減少します。そのため、減価償却として減少分を毎年計上するのですが、その固定資産の収益性が低下すると、減価償却が終わる前に帳簿価額の回収が見込めなくなることがあります。
その場合、帳簿価額を減額し、不足分を損失として処理することで、固定資産の価値を適切なものに修正できます。これが減損会計、減損処理を行う目的です。
減損会計を行うことで、財務諸表は正確性を保ち、企業の本当の経営状態が決算書類に反映されることになります。企業の現状を正しく把握するためにも、減損会計は必要です。

2.減損損失を判定する流れ
減損会計は上場企業や大企業では義務付けられており、この場合「固定資産の減損に係る会計基準」で定められたルールに従って処理を行います。一方、非上場の中小企業は減損会計が義務付けられていません。
「固定資産の減損に係る会計基準」で定められたルールでは、次のフローで減損損失を判定します。
2-1.資産のグルーピング

まずは「資産のグルーピング」をします。固定資産を最小単位のグループに分け、そのグループごとに減損損失の影響を測定します。
最小単位のグループは、「他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位」と規定されています。
2-2.減損の兆候の把握
グルーピングした資産ごとに、減損の兆候があるかを把握します。例えば、次のようなケースは「減損の兆候がある」と考えられます。
- 営業損益が2期以上連続でマイナスになった
- 投資資産の回収可能価額が著しく低下した
- 経営環境が著しく悪化した
- 投資した資産の市場価格が著しく落下した
こうした「減損の兆候」がない場合、減損会計は不要です。
2-3.減損損失の認識の判定~測定
「減損の兆候がある」と判断した資産を実際に減損すべきか判定します。
判定は、「その資産が将来的に生み出す利益と、資産の処分によって得られる総額」と「帳簿価額」を比較して行います。
前者が帳簿価額を下回った場合は、帳簿価額を回収可能額まで減額し、減少額を減損損失として計上します。
出典:固定資産の減損に係る会計基準の適用指針|企業会計基準委員会
3.財務諸表への影響
減損会計が、財務諸表に与える影響について説明します。
3-1.貸借対照表への影響

減損損失を計上した場合、固定資産の簿価を直接減額します。
そのため、減損損失を計上した分だけ、資産総額が小さくなります。
3-2.損益計算書への影響
減損損失は、損益計算書に特別損失として計上され、その分だけ当期純利益が減少します。
しかし、固定資産の簿価が減少することから、翌期からの減価償却費も減少します。そのため、翌期以降の純利益は改善すると言えます。
3-3.キャッシュフロー計算書への影響
減損損失を計上しても、現金の流出があるわけではないため、当期のキャッシュフロー計算書には影響がありません。
一方で、減損損失を計上することは、将来的なキャッシュフローの低下を意味しており、翌期以降のキャッシュフロー計算書には影響があります。
4.まとめ
減損記事の概要から、実務的な判定方法、財務諸表への影響まで幅広く解説しました。減損損失の理解を深め、適切に活用することは、的確な経営判断や投資判断に繋がるでしょう。
一方で、減損会計のプロセスは複雑であり、誤りがあると巨額の損失に繋がりかねません。そのため、状況に応じ、公認会計士などの専門家に相談することをおすすめします。
受発注業務の効率化にカシオの「BC受発注」
カシオのBC受発注は、受発注業務の効率化に最適です。得意先から発注が来るとメールや画面上のアラートでお知らせするので、うっかり忘れることがなくなり、内容を確認したら「受注取り込み」をクリックするだけで販売管理システムに発注データを自動連携できます。
電話やFAX、メールなどバラバラな手段で発注を受ける必要がなくなり、入力にかかる手間も大幅に削減できます。さらに、受注した後の入力ミスも起こらなくなるため、得意先からの信頼もアップするでしょう。
発注を行う得意先は、パソコンやタブレット、スマートフォンから専用ページにアクセスして発注すればよく、得意先ごとの商品マスタも用意できるため、操作は難しくありません。従来の発注方法からの切り替えをお願いしやすくするツールも揃っており、スムーズに受発注業務のDX化を進められるはずです。
以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://web.casio.jp/bc-order/
