
コラム

「損益分岐点」をわかりやすく解説します
2024.11.20|最終更新日:2024.11.20
事業の売上高と、固定費・変動費などの経費がちょうど釣り合い、赤字も黒字もないポイントのことを「損益分岐点」といいます。損益分岐点を達成し、それ以上の売上は利益となるため、経営状況を測るためにも大切な指標です。
しかし、損益分岐点という言葉を知っていても、計算したことのない人は少なくないかもしれません。そこでここでは、損益分岐点の基本をわかりやすく解説するとともに、損益分岐点を把握するメリットや、損益分岐点を下げて経営を安定させるヒントなどを紹介します。
目次

1.損益分岐点とは?その構成要素と計算方法
1-1.損益分岐点とは

損益分岐点とは、売上高と経費の額が同じで、赤字でも黒字でもないときの売上高のことです。正確には「損益分岐点売上高」と呼ばれ、赤字を出さない経営のための指標となります。
損益分岐点売上高を上回れば黒字、下回れば赤字となるため、最低限必要な売上高といえます。事業において欠かせない重要な知識です。
1-2.固定費
固定費とは、売上に関係なく毎月発生する一定の支出のことです。店舗運営で固定費に該当する経費として、次のようなものが挙げられます。
- 地代・家賃
- 各種リース料
- 支払利息
- 減価償却費
- 水道光熱費の固定契約料
- 人件費(月給制の社員、契約社員など)
固定費が大きいと継続的な支出が増えるため、より大きな売上が必要となり、黒字化へのハードルが高くなります。反対に、固定費が小さければ支出が減り黒字化しやすくなります。経営を安定させるためには、固定費を抑えることが大切です。
1-3.変動費
変動費とは、月によって金額が変動する支出のことです。店舗運営で変動費に該当する経費として、次のようなものが挙げられます。
- 仕入れ費
- 消耗品費
- 水道光熱費
- 販促費
- 人件費(パート・アルバイトなど)
変動費も固定費と同様に、少ないほうが黒字化しやすくなります。一方で、削減することでサービスの質が下がってしまう性質のものも多く、ただ下げればいいものではありません。しかし、工夫次第でサービスの質を落とさずに変動費を下げることも可能です。
1-4.損益分岐点売上高の計算方法
損益分岐点売上高は、次の計算式で求められます。
- 固定費 ÷ (1-変動費 ÷ 売上高)
例えば、固定費が50万円、変動費が40万円、売上高が100万円の事業があったとします。これを損益分岐点売上高の計算式に当てはめると、次のようになります。
- 50万円 ÷ (1-(40万円 ÷ 100万円)) = 833,333…円
この事業における損益分岐点は、約83万円であることがわかります。

2.損益分岐点を把握するメリット
2-1.黒字化に必要な売上高がわかり売上目標が立てられる

損益分岐点を把握することで、黒字化に必要な売上高の目安がわかるようになります。そして、売上目標が立てられるようになります。
損益分岐点は、赤字の店舗だけでなく、黒字の店舗でも把握しておくほうがよいでしょう。今まで黒字が続いてきた理由がわかれば、知らず知らずのうちに赤字転落することを避けられます。
2-2.売上目標達成のために許容できる経費がわかる
損益分岐点を把握することで「どこから赤字になるか」がわかるようになります。赤字の店舗が経営改善の指標にできることはもちろん、経営が順調だったために、危機感なく固定費や変動費を増やしすぎてしまうことを防げるはずです。
また、損益分岐点を把握しておくことで、商品やサービスを値下げしすぎてしまうことも防げます。反対に、商品原価が値上がりした際、どのくらい値上げをすれば同等の経営水準を保てるかの指標としても役立つでしょう。
2-3.経営状態の判断がしやすくなる
損益分岐点を把握し、黒字化に必要な売上高や、許容できる固定費・変動費の目安がわかることで、経営状態が大まかに見えてきます。
例えば、損益分岐点を活用して事業の状態を評価する指標である「安全余裕率」の計算が可能になります。安全余裕率は次の計算式で求めます。
- (売上高 ー 損益分岐点売上高) ÷ 売上高 × 100(%)
安全余裕率は、売上高の減少がどの程度までであれば損失が生じないかを示す比率です。損益分岐点が低く、売上高が高いほど安全余裕率が高くなります。
例えば、売上高が100万円、損益分岐点売上高が83万円の事業があったとします。これを安全余裕率の計算式に当てはめると「17%」となり、あと17%売上が下がっても赤字にならないことを示しています。
これはあくまで判断の一例ですが、損益分岐点を計算し把握することは、経営状態の判断の基礎といえるでしょう。
3.損益分岐点を下げる方法
3-1.固定費を下げる
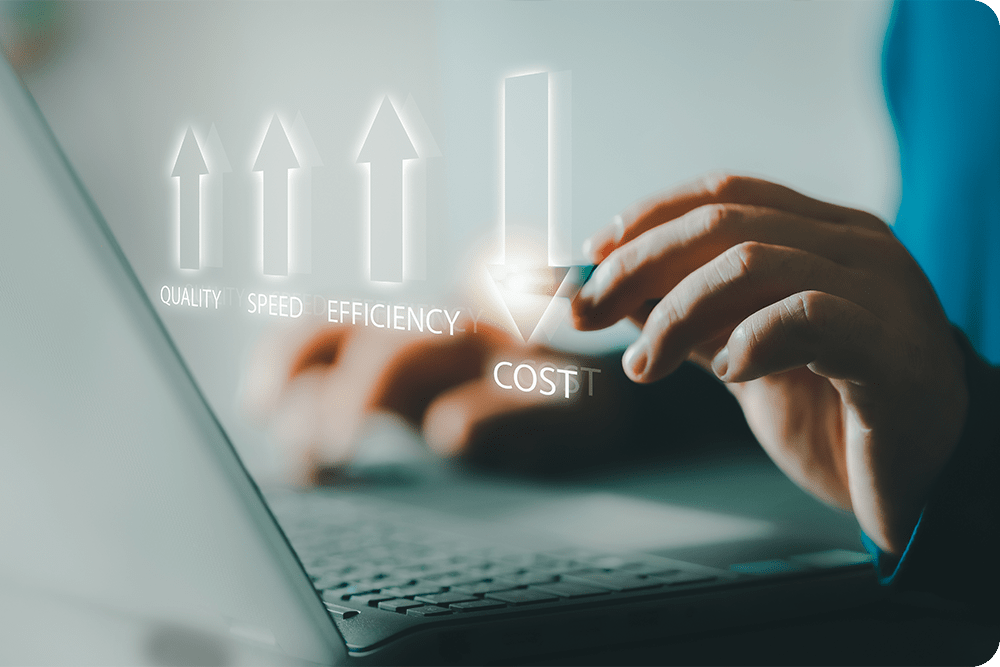
店舗運営における大きな固定費として、まず家賃が挙げられます。すでに長く契約をしていて、契約の更新時期が近い場合などは、値下げ交渉の余地があるかもしれません。その際は、事前に周辺の家賃相場も確認するとよいでしょう。また、日頃から大家側と良好な関係を築いておくことも大切です。
また、インターネット回線や、業務用の携帯電話回線なども見直す余地があるでしょう。インターネットは新しい事業者も続々と登場していますし、携帯電話はMVNO(格安SIM)を利用することで大幅な値下げが可能です。契約が古いままの場合は見直してみるとよいでしょう。
融資(ローン)にかかる利息を確認することも大切です。民間金融機関からの借入がある場合は、より有利な条件で借り換えることで、毎月の支払利息を少なくできる可能性があります。また、条件に合えば、日本政策金融公庫や地方自治体による低金利の融資制度を利用できる場合もあるため、確認するとよいでしょう。
3-2.変動費を下げる
変動費は、削減することでサービスの質が下がってしまう性質のものが含まれるため、慎重に検討することが大切です。
例えば、電気・ガスの契約を見直すことで利用料を下げられる場合があります。電気はすでに自由化されており、ガスはLPガスだけでなく、地域によっては都市ガスも自由化されています。随分前に契約をしてそのままの場合は、見直す余地があるはずです。
仕入れに関わる経費を見直すことも大切です。小売店であれば、今より安価に仕入れられる方法を調べた上で、まずは現在の仕入れ先と交渉してみる方法があります。また、飲食店の場合は、仕入れ先との交渉や、仕入先の変更に加え、食品ロスを減らして仕入れ量を見直す方法もあります。
こうした方法であれば、サービスの質を下げることなく変動費の見直しが可能です。
3-3.販売単価を上げる
販売単価を上げる、つまり値上げをすることは、損益分岐点を下げるためにもっとも効果的な方法です。例えば、10%の値上げができれば売上も10%アップするため、大きな収益の改善が見込めます。
特に、仕入れる商品や食材の原価が上がった場合、損益分岐点を利用した計算を行い、販売単価を見直すことが大切です。価格競争になってしまうと、資本力のある大企業には一般的にかないませんし、薄利多売になり消耗してしまいます。
そのため、他にないサービスや体験を提供するなど、販売単価を上げる工夫を行うことが大切になるでしょう。
4.まとめ
損益分岐点は、事業の経営状態を判断するために役立ちます。どうすれば黒字化できるか、売上目標を達成するためにどのくらいの経費をかけてよいかなどがわかるため、経営の方針や目標がより明確になるはずです。
また、損益分岐点を下げることができれば、収益が安定し経営に余裕ができます。そうすれば、サービスの向上のために予算と労力を使えるようになるでしょう。損益分岐点を把握していない経営者の方は、このコラムを参考に計算してみてはいかがでしょうか。
受発注業務の効率化にカシオの「BC受発注」
カシオのBC受発注は、受発注業務の効率化に最適です。得意先から発注が来るとメールや画面上のアラートでお知らせするので、うっかり忘れることがなくなり、内容を確認したら「受注取り込み」をクリックするだけで販売管理システムに発注データを自動連携できます。
電話やFAX、メールなどバラバラな手段で発注を受ける必要がなくなり、入力にかかる手間も大幅に削減できます。さらに、受注した後の入力ミスも起こらなくなるため、得意先からの信頼もアップするでしょう。
発注を行う得意先は、パソコンやタブレット、スマートフォンから専用ページにアクセスして発注すればよく、得意先ごとの商品マスタも用意できるため、操作は難しくありません。従来の発注方法からの切り替えをお願いしやすくするツールも揃っており、スムーズに受発注業務のDX化を進められるはずです。
以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://web.casio.jp/bc-order/
