
コラム

【今さら聞けない】
卸売業の「システム」に関する専門用語5選
(RPA、EOS、EDI、JANコード、トレーサビリティ)
2025.01.31|最終更新日:2025.01.31

現代の卸売業において、効率的な業務運営には高度なシステムの活用が欠かせません。しかし、専門用語が多く、初心者には理解が難しいことも少なくありません。
ここでは、卸売業界で重要とされるシステム関連の専門用語「RPA」「EOS」「EDI」「JANコード」「トレーサビリティ」について、基本的な意味と導入効果について解説します。
目次

1.RPA
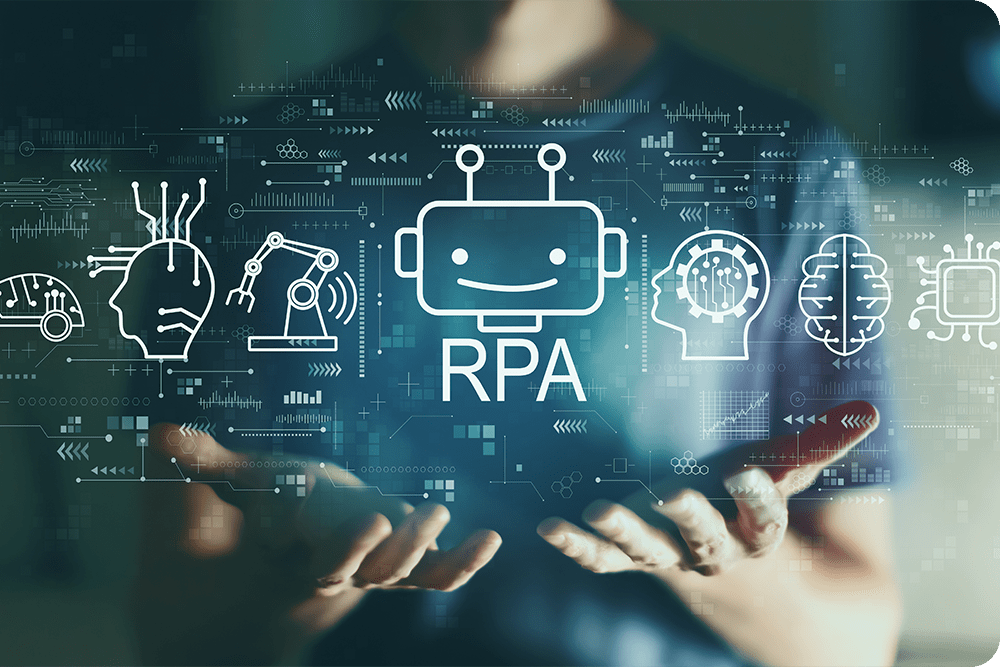
RPAは「Robotic Process Automation」の略で、これまで人間が行ってきたパソコン上の定型作業を自動化する技術のことを指します。
主に、データ入力やファイル操作、アプリケーション間でのデータ転記といった反復的な作業を、人間の代わりにソフトウェアロボットが実行するものです。
RPAのメリットは、既存のシステムを大きく変更することなく導入できる点と、プログラミングの知識がなくても、ソフトウェアによる直感的な操作で自動化が可能な点にあります。
導入効果として、作業時間の大幅な短縮、人的ミスの削減、業務効率の向上が挙げられます。特に、複数のシステムを跨いで行う定型作業の自動化に効果を発揮し、働き方改革や人材不足への対応策として注目されています。

2.EOS
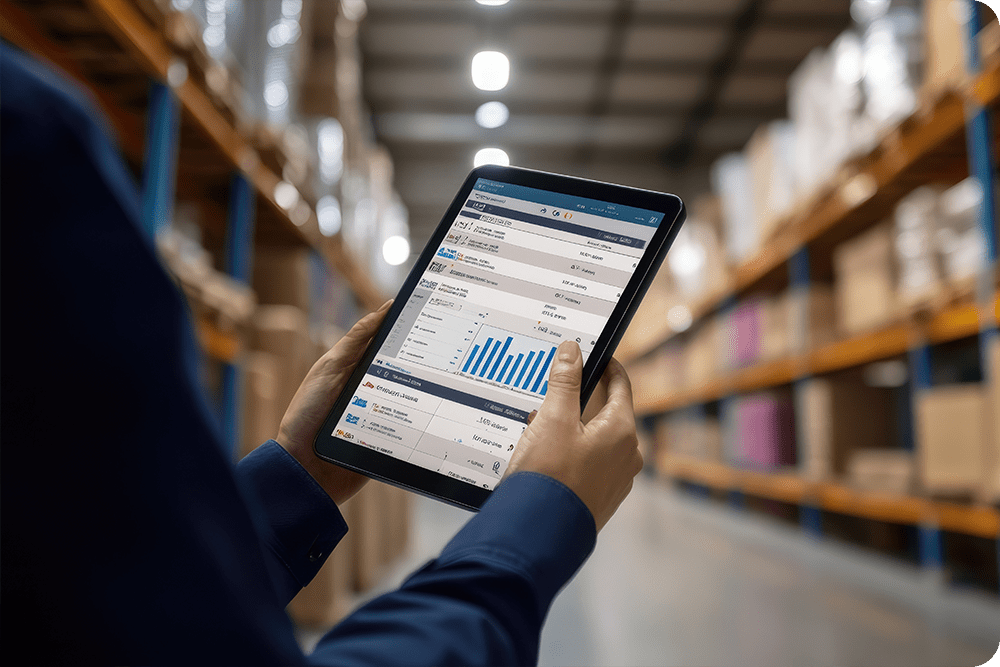
EOS(Electronic Ordering System)は、企業間でオンラインを通じて受発注データを交換するシステムのことで、日本語では「電子発注システム」と呼ばれます。
従来、電話やFAXで行っていた発注業務を、コンピューターとネットワークを利用して電子化することで、業務の効率化を実現するものです。
具体的には、発注者がタブレットなどの端末で在庫確認や発注数量の入力を行うと、その情報が自動的にホストコンピューターを経由して卸売業者やメーカーに送信され発注が完了します。これにより、発注業務の省力化や、納品リードタイムの短縮、在庫の適正化などが可能になります。
EOSは1970年代から小売業と卸売業の間で導入が始まり、現在ではPOSシステムとの連動、在庫管理システムとの連携により、売上情報の一元管理や自動発注処理なども実現しています。さらに、後述するEDIの一部としても組み込まれ、受発注から支払いまでを一括で行えるシステムへと進化しています。
3.EDI
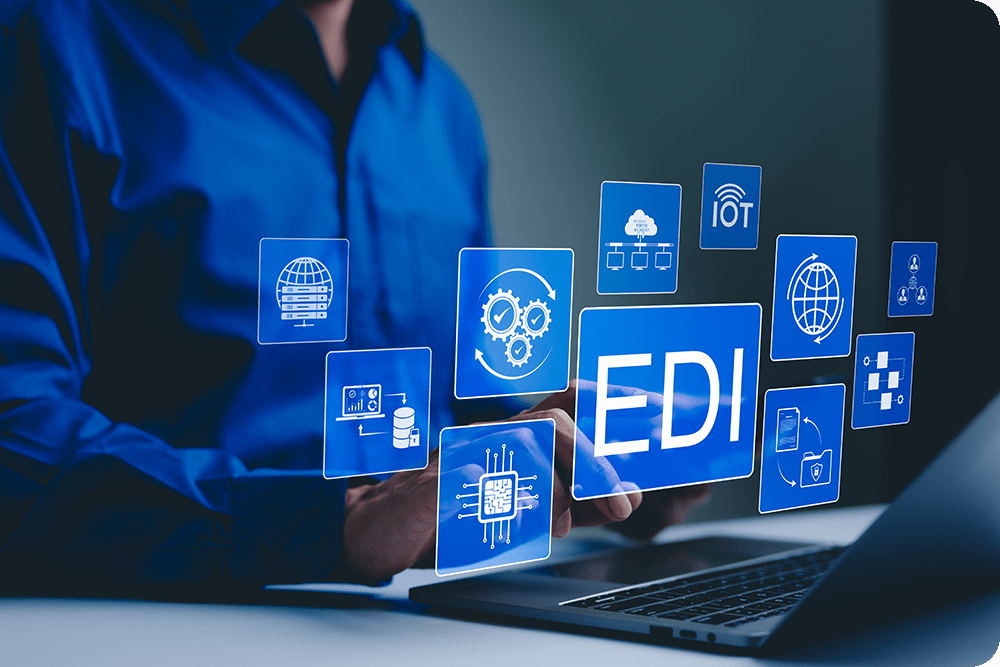
EDI(Electronic Data Interchange)は、企業間でビジネス文書を標準的な電子データ形式で交換する仕組みで、日本語では「電子データ交換」と呼ばれます。
EDIを導入することで、従来、紙ベースで行われていた発注書や請求書などを、コンピューターシステム間で直接やりとりできます。これにより、手作業の処理時間を短縮し、エラーの削減や、データの可視化といったメリットが得られます。
EDIには主に2つの通信タイプがあります。一つは仲介者を介さず直接接続する「ダイレクトEDI(ポイント・ツー・ポイント EDI)」で、もう一つはサードパーティーのネットワークを介して管理する「付加価値ネットワーク(VAN)」です。
さらに、一般的なインターネット回線とウェブブラウザを用いる「Web-EDI」と、専用の通信機器を使ってセキュリティを重視した「インターネットEDI」があります。用途やコストに応じて選ばれますが、「インターネットEDI」は自動化が可能となっており、今後さらに注目されるものと考えられます。
4.JANコード

JANコードは「Japanese Article Number」の略称で、商品を識別するための国際的な番号体系です。日本で使用される商品のバーコードの多くがこのJANコードを採用しています。
JANコードは8桁もしくは13桁の数字で構成され、商品パッケージに印刷されます。この体系は世界的に統一されており、北米ではUPC、ヨーロッパではEANとして知られています。
JANコードは以下の3つの要素で構成されています。
- GS1事業者コード(前半7桁、9桁、10桁のコード)
- 商品アイテムコード(GS1事業者コードの次の3桁)
- チェックデジット(最後の1桁)
運用にあたっては、一つの商品(取引単位)につき一つのコードを設定する必要があります。また、終売した商品のコードを別の商品に再利用することは禁止されています。
5.トレーサビリティ

トレーサビリティ(Traceability)は、製品や部品の生産から消費・廃棄までの過程を追跡できる状態を指します。「追跡(Trace)」と「能力(Ability)」を組み合わせた造語で、日本語では「追跡可能性」と訳されます。
トレーサビリティのメリットは、製品に問題が発生した際の迅速な対応が可能になる点です。不具合や品質問題が見つかった場合、その製品がいつ、どこで、どのように製造され、どのような経路で流通したのかを即座に特定できます。問題のある製品の迅速な回収や原因究明が可能となるため、被害を最小限に抑え、消費者からの信頼維持にもつながります。
日本では2003年のBSE(いわゆる狂牛病)問題を契機に、トレーサビリティの重要性が広く認識されました。現在はICタグやQRコード、ブロックチェーンなどの先端技術を活用し、食品業界に限らず、製造業、医薬品業界、アパレル産業など幅広い分野での導入が進んでいます。
なお、トレーサビリティには大きく2種類あります。
チェーントレーサビリティ
原材料の調達から、製造・加工、流通、販売に至るまでのサプライチェーン全体を通じて、製品の移動を追跡できる仕組みです。各段階での履歴情報を記録・保管することで、製品の流通経路を完全に把握することができます。
内部トレーサビリティ
企業内や工場内など、特定の組織内での製品や部品の移動を追跡する仕組みです。こちらは、製造工程での品質管理や在庫管理に特に重要な役割を果たします。
受発注業務の効率化にカシオの「BC受発注」
カシオのBC受発注は、受発注業務の効率化に最適です。得意先から発注が来るとメールや画面上のアラートでお知らせするので、うっかり忘れることがなくなり、内容を確認したら「受注取り込み」をクリックするだけで販売管理システムに発注データを自動連携できます。
電話やFAX、メールなどバラバラな手段で発注を受ける必要がなくなり、入力にかかる手間も大幅に削減できます。さらに、受注した後の入力ミスも起こらなくなるため、得意先からの信頼もアップするでしょう。
発注を行う得意先は、パソコンやタブレット、スマートフォンから専用ページにアクセスして発注すればよく、得意先ごとの商品マスタも用意できるため、操作は難しくありません。従来の発注方法からの切り替えをお願いしやすくするツールも揃っており、スムーズに受発注業務のDX化を進められるはずです。
以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://web.casio.jp/bc-order/
