
コラム

「納期遅延時のお詫び」のビジネスメールで大切なことは? 書く内容・例文を紹介します
2025.03.31|最終更新日:2025.03.31
ビジネスシーンでは、ときに予期せぬ事情で納期に遅れが生じることもあります。そんなとき、どのように対応すれば相手の不安を解消し、信頼を損なわずに済むのでしょうか。
ここでは、納期が遅れてしまった場合に送るお詫びメールの書き方や、意識しておきたいポイントを例文と共に解説します。取引先にしっかりと誠意を伝えるための参考になるはずです。
目次
- 1.納期遅延をお詫びするメールに書く内容
- 1-1. 納期遅延の報告とその理由の説明
- 1-2. 新たな納品日の見通し
- 1-3. 誠意をもってお詫び、謝罪
- 1-4. 今後の対策(対策可能な場合)
- 2.納期遅延のお詫びメールで大切なこと
- 2-1. 納期遅延がわかったらすぐに送る
- 2-2. 件名はわかりやすく
- 2-3. 時候の挨拶は省略する
- 2-4. 宛先・CC・BCCの設定は的確に
- 2-5. 緊急の場合は電話でも報告・謝罪を
- 3.納期遅延時のお詫びの例文を紹介
- 3-1. 【例文1】自社のミスが原因で遅延した場合
- 3-2. 【例文2】想定外の受注増で遅延した場合
- 3-3. 【例文3】天候や自然災害など不可抗力で遅延した場合
- 3-4. 【例文4】電話も合わせて使う場合の補足例
- 4.まとめ

1.納期遅延をお詫びするメールに書く内容
納期が遅れることがわかったら、まずは事実を遅滞なくお知らせしましょう。しかし、ただお詫びするだけでなく、いくつかの点に気を付けることで先方の心象が良くなるはずです。
1-1.納期遅延の報告とその理由の説明

まず冒頭で「納期が遅れる」ことを端的に述べ、続けて「なぜ遅れているのか」、その理由をわかりやすく書きましょう。相手が知りたい事実を正直に伝えることを心がけましょう。
このとき、原因が外部にある場合でも、言い訳せずに誠実な対応を心がけることが大切です。
また、自社の受注ミスや生産ラインのトラブルなどは、その時は怒られるかも知れませんが、ありのまま伝えたほうが結果的に信頼を得られると考えられます。
1-2.新たな納品日の見通し
納期が遅延する場合、相手が気になるのは「いつ納品されるか」です。そのため、できるだけ具体的な納品スケジュールを示すことが望ましいと考えられます。
新たな納品日が確定していない段階でも、大まかな見込みを示し、確定したら追って連絡する旨を伝えましょう。相手の不安を和らげることに繋がるはずです。
このとき、あまりタイトな日程にせず、余裕を持った日程を伝えましょう。重ねての遅延を避けるコツとなります。
1-3.誠意をもってお詫び、謝罪
納期遅延を連絡するメールでは、「ご迷惑をおかけしている」という謝意をわかりやすく言葉にしましょう。文面の途中と締めくくりの両方でお詫びの気持ちを示すことで、相手への配慮を欠かしていない姿勢が伝わるはずです。
自社に落ち度がない場合も、相手にとっては予定が狂わされる事実に変わりはありません。そのため、自社に責任がないかのような文面は避けるべきです。へりくだる必要はありませんが、誠意をもった対応が大切です。
1-4.今後の対策(対策可能な場合)
遅延の原因が自社にある場合、可能であれば、今後の対策について書き添えましょう。相手との関係を修復し、信頼を回復する材料になります。
再発防止策を詳しく書く必要はありませんが、簡潔にでも記しておくことで、「今後、同じ遅れは起こらないだろう」という安心感をもっていただける可能性が高くなります。誠意もより伝わるはずです。

2.納期遅延のお詫びメールで大切なこと
メールの内容やタイミングを誤ると、先方を不安にさせてしまったり、怒らせてしまったりといったことがあります。ここでは、お詫びメールで大切なことを解説します。
2-1.納期遅延がわかったらすぐに送る
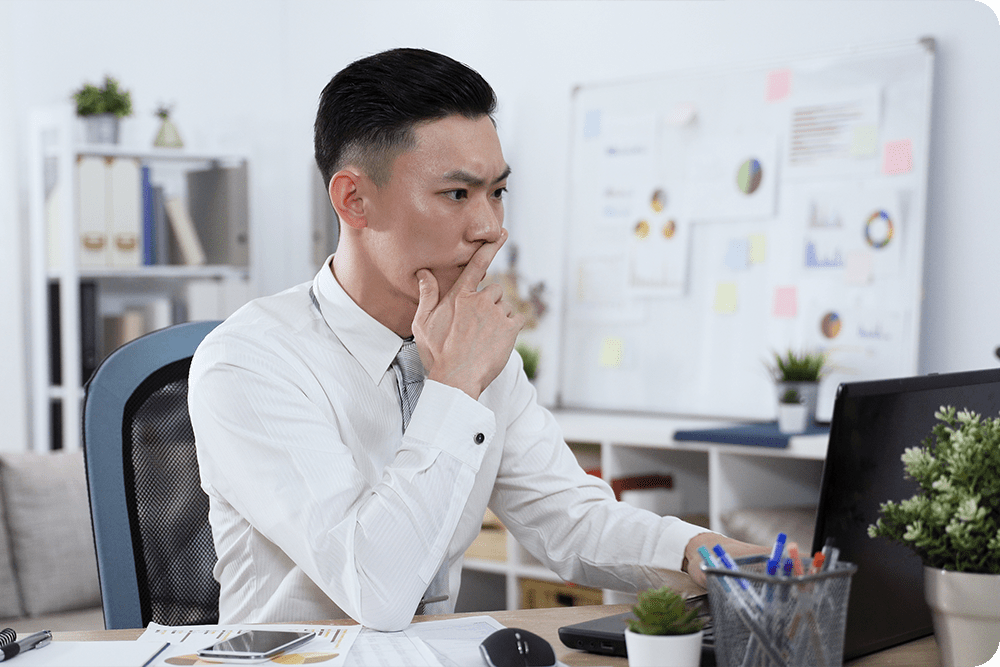
納期遅延はできる限り早く連絡をしましょう。納品が間に合わないことがわかった段階で、ためらわずに連絡するのが賢明です。
また、納期が遅れそう…と判明した時点で連絡したほうが親切な場合もありますが、先方との関係や遅延の内容にもよるため、ケースバイケースの判断となるでしょう。
連絡が後手に回るほど不信感を与えますし、先方が計画を変更する余裕をなくしてしまうかもしれません。先方のことを考え、早め早めに対応しましょう。
2-2.件名はわかりやすく
ビジネスメールは日々大量に受信しているケースが多く、多くのメールの中に埋もれてしまう可能性もあります。
そのため、件名を「納期遅延に関するお詫び」などと簡潔にし、「一刻も早く確認すべき内容」であることが伝わるようにすることが大切です。さらに、件名の冒頭に【重要】などを付けることで、見落とすリスクを下げられます。
2-3.時候の挨拶は省略する
納期遅延を伝えるメールでは、要点を的確に伝えることが最優先となります。そのため、一般的なビジネス文書で使う時候の挨拶は省略して差し支えありません。
前置きが長いと、かえって混乱を招く場合もあるので、端的に伝えることを心がけると良いでしょう。
2-4.宛先・CC・BCCの設定は的確に
遅延連絡のメールを送る際、担当者一人にメールを送るのではなく、先方の上司や、自社の他部署にも情報を共有したほうが良いケースがあります。
そういった場合は、メインの担当者のメールアドレスをToに、それ以外に情報を共有したほうが良いと思われる人のメールアドレスをCCに入れます。さらに、自社の上司や他部署の担当者をBCCに入れることで、先方から見えない形で共有可能です。
こうすることで、遅延に関する情報の共有がスムーズになり、後々のトラブル防止に役立ちます。遅延の情報を誰に共有すべきかを考えながら、宛先を設定しましょう。
2-5.緊急の場合は電話でも報告・謝罪を
受注金額が大きいケースや、納期直前など切迫した状況では、納期遅延をメールで伝えるだけでなく、電話での報告と謝罪が必要です。先方にとっての不利益が大きい状況では、より誠実に対応することが大切になります。
一方、メールには記録が残るメリットがあります。メールを送ってすぐに電話をする、もしくは電話をしてから詳細をメールで送るといった方法で、メールと電話を併用すると良いでしょう。
3.納期遅延時のお詫びの例文を紹介
ここからは、納期遅延の理由ごとに、お詫びの例文を紹介します。
3-1.【例文1】自社のミスが原因で遅延した場合
件名:【重要】納期遅延のお詫びと新たな納品予定について
【本文】
○○株式会社 ○○部 ○○様
平素より大変お世話になっております。××株式会社の□□です。
このたび、ご注文いただいておりました商品「○○」の納品に遅延が生じてしまいました。弊社内での受注処理に不備があり、出荷の手配が遅れてしまったことが今回の原因でございます。誠に申し訳ございません。
現在、速やかに出荷準備を進めておりますが、新たな納品日につきましては、○月○日頃を予定しております。大変ご不便をおかけし、深くお詫び申し上げます。
今後はこのようなミスが再発しないよう、受注管理と在庫確認の体制を強化すると共に、社内のチェックフローを見直してまいります。
略儀ではございますが、取り急ぎ、メールにてお詫びと今後の対応をお知らせ致します。何かご要望やご不明点がありましたら、遠慮なくお申し付けください。
納期の遅延によりご迷惑をおかけすること、重ねてお詫び申し上げます。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
3-2.【例文2】想定外の受注増で遅延した場合
件名:【重要】○○の納期遅延に関するお詫びとご報告
【本文】
○○株式会社 ○○部 ○○様
いつも弊社商品をご利用いただき、誠にありがとうございます。××株式会社の□□でございます。
このたび、ご注文いただいております「○○」につきまして、想定を上回る注文をいただいた影響から在庫が不足し、納期に遅れが生じる見込みとなりました。心よりお詫び申し上げます。
新たな納品時期は○月○日(○)頃を見込んでおります。お急ぎのところ誠に申し訳ございません。
今後このような事態を繰り返さぬよう、在庫管理と生産体制の両面を強化し、より正確な納期見通しを立てられるよう改善を進めてまいります。
納期の遅延によりご迷惑をおかけすること、重ねてお詫び申し上げます。
正式な納品日が確定次第、改めてご連絡申し上げますが、ご不明などございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
3-3.【例文3】天候や自然災害など不可抗力で遅延した場合
件名:【重要】大雨による納期遅延のお知らせとお詫び
【本文】
○○株式会社 ○○部 ○○様
いつも弊社サービスをご利用いただき、ありがとうございます。××株式会社の□□でございます。
先日の大雨(または台風・地震など)の影響により、物流網の一部が停止しており、○○様にお届けする商品の到着が大幅に遅れております。
すでに運送会社と協議のうえ、可能な限り早い配送を手配しておりますが、納品日については○月○日(○)頃になる見込みです。
本来であれば○日までにお届けすべきところ、天候不良とはいえ結果としてご迷惑をおかけしてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。今後は災害時でも迅速な対応ができるよう、在庫の保管方法や輸送ルートの見直しを検討してまいります。
ご希望の到着日時や配送方法などに追加のご要望がございましたら、遠慮なくお知らせください。
このたびは多大なるご不便をおかけしましたことを重ねてお詫びいたします。何卒ご理解いただけますと幸いです。
3-4.【例文4】電話も合わせて使う場合の補足例
件名:【至急】○○の納期遅延に関するご連絡とお詫び
【本文】
○○株式会社 ○○部 ○○様
いつも大変お世話になっております。××株式会社の□□でございます。
先ほどお電話でもお伝えいたしましたが、○○の納期が遅れることになり、誠に申し訳ございません。
運送会社のトラブルにより出荷が一時停止となっているため、現状では○月○日(○)頃の納品予定となります。進捗状況がわかり次第、再度ご連絡いたします。
この度は、納期の遅延によりご迷惑をおかけし申し訳ありません。今後は運送業者との連携を強化すると共に、納品管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。
引き続き、宜しくお願い申し上げます。
4.まとめ
納期遅延は避けたいトラブルですが、どうしても避けられない場面があるのも事実です。だからこそ、遅れるとわかった段階で速やかに連絡し、その理由を正直に伝えたうえで、新たな納品日をできるだけ具体的に示すことが大切になるでしょう。
メールや電話で誠意をもってお詫びし、今後の対策を伝えるだけでも、相手の不安はかなり和らぐはずです。ここで紹介した例文やポイントを参考に、適切で誠意ある謝罪メールを送り、取引先との信頼関係を築きましょう。
受発注業務の効率化にカシオの「BC受発注」
カシオのBC受発注は、受発注業務の効率化に最適です。得意先から発注が来るとメールや画面上のアラートでお知らせするので、うっかり忘れることがなくなり、内容を確認したら「受注取り込み」をクリックするだけで販売管理システムに発注データを自動連携できます。
電話やFAX、メールなどバラバラな手段で発注を受ける必要がなくなり、入力にかかる手間も大幅に削減できます。さらに、受注した後の入力ミスも起こらなくなるため、得意先からの信頼もアップするでしょう。
発注を行う得意先は、パソコンやタブレット、スマートフォンから専用ページにアクセスして発注すればよく、得意先ごとの商品マスタも用意できるため、操作は難しくありません。従来の発注方法からの切り替えをお願いしやすくするツールも揃っており、スムーズに受発注業務のDX化を進められるはずです。
以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://web.casio.jp/bc-order/
