
コラム

卸売業はなくなる? その背景とIT化による生き残り戦略とは
2025.03.31|最終更新日:2025.03.31
メーカーと小売店の直接取引が増える中、「卸売業がなくなるのでは?」とも囁かれています。
実際のところ、卸売業の果たす役割は大きく、卸売業はなくならないという見方をする人が多い状況ですが、その一方で、IT・DX化が進まない卸売業者にとっては状況が厳しくなりつつあることも事実と言えます。
ここでは、卸売業はなくなるのか?という疑問に答えつつ、卸売業が生き残るためのIT化・DXの重要性について解説します。
目次

1.「卸売業がなくなる」と言われる背景
「卸売業がなくなる」という見方には複数の要因が絡んでいると考えられます。ここでは、その主な背景について解説します。
1-1.卸売業の販売額が長い間減り続けていた

卸売業がなくなると囁かれる一つ目の背景は、卸売業全体における販売額が実際に減り続けていたことです。
経済産業省が調査を行っている商業動態統計調査によれば、1980年時点での販売額は約359兆円、1991年には約566兆円となりピークを迎えます。しかし、2019年には約356兆円まで減ってしまいました。
業種別に細かく見ていくと、食料品や飲料の小売業では大きな変化がない一方、繊維品卸売業や家具などの卸売業は、1990年代のピークから売上を大きく減らしてきました。
出典:商業動態統計調査 時系列データ|経済産業省
1-2.メーカーの直接販売が増えている
従来は、メーカーと小売業者の間に卸売業者が入る取引形態が一般的でした。卸売業者はメーカーから商品を仕入れ、そこから多くの小売業者に納品する物流も担っていたのです。
しかし近年、インターネットとECサイトの普及、そして物流網のさらなる発達により、メーカーが小売業者や消費者に直接販売できる状況が整いました。そのため、卸売業者を挟まない取引が増え、これも卸売業の未来を危惧する一因となっているのです。
1-3.卸売業者のIT化・DXが遅れている
近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が叫ばれ、卸売業界にもIT化の波が押し寄せています。しかし、今でも比較的小規模な卸売業者では、FAXや電話を軸に人力で注文を処理する従来の受発注方式に頼っているケースが少なくありません。
アナログな受発注方式は、入力ミスや確認漏れを招きやすく、処理コストも高くなります。時代が求める効率化やスピードに追い付けていないことから、「このままでは競争に取り残されるのでは」と懸念されています。

2.「卸売業はなくならない」と言える理由
卸売業の今後を懸念する声もありますが、実際には卸売業がすべて消滅することはないと考えられています。その理由を解説します。
2-1.卸売業の販売額が再び増えている
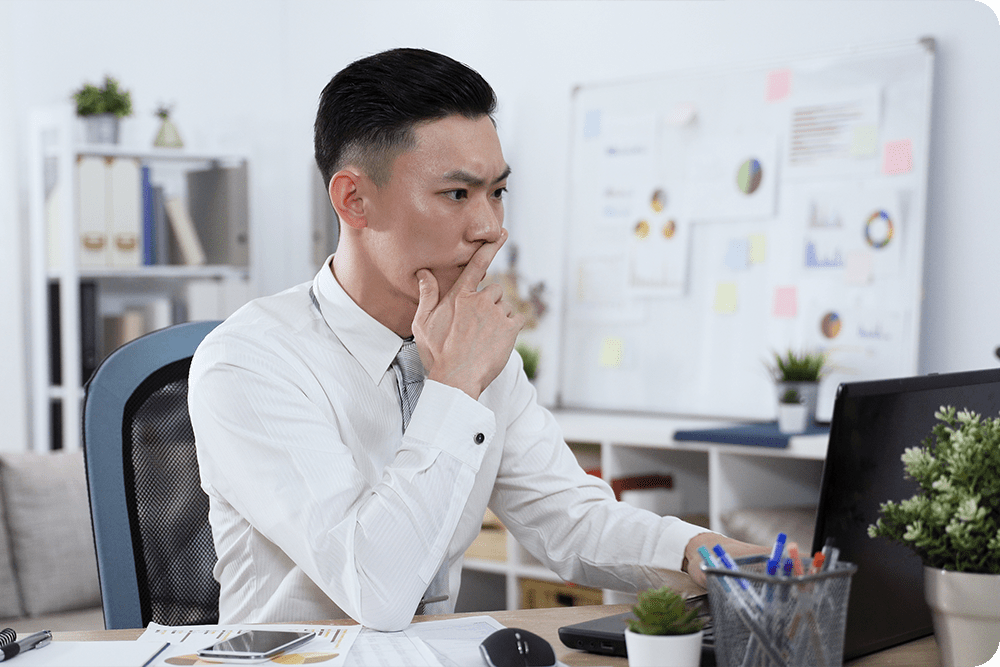
業種により若干のズレはあるものの、2020年頃を境に、卸売業の販売額は再び増え始めています。
これは、長く続いた不景気が好転し始めたことや、都心を中心とした建設ラッシュ、また、2020年初頭から始まった新型コロナウイルスの影響により、人々の生活様式に変化が生じたことなどが要因と考えられます。
2019年に約356兆円まで減った卸売業の販売額は、2021年には13年ぶりに400兆円を超え、2024年には約445兆円まで回復。今後もしばらくこうした流れが続くと考えられています。
2-2.一種のコンサルとして機能している
日本では、1960年代にも卸売業がなくなる「問屋無用論」が唱えられた時期がありました。大量生産・大量消費が進む中で店舗のチェーン店化が進み、小売業者とメーカーの直接取引が可能になったことがその発端です。
しかし、それから60年以上が経った今も、問屋(卸売業者)は生き残っています。その主な理由は、欧米ほど小売市場の寡占化が進まなかったことや、日本の卸売業者が独自の進化を遂げたことにあると考えられます。
卸売業者はメーカー・小売店の両方と関わるため、市場の様々な情報や、商品の動向を集めやすい立場です。消費者のトレンドをいち早く把握し、メーカーに活用を促したり、小売業へ売場提案を行ったりすることで、単なる仲介を超えた「コンサル」としての役割を果たしてきた背景があります。
こうした日本独自の文化は明治時代に遡り、問屋がメーカーを育ててきた側面もあります。こうした日本独自の卸売業者の立場は、今後も簡単に失われるものではないと考えられ、「卸売業はなくならない」と考える理由の一つになっているのです。
2-3.多品種小ロットでも安定した仕入れが可能になる
日本国内の流通では、多品種の商品を小ロットで発注するケースが多々あります。こうした細分化されたニーズをまとめて効率よく供給できることは、日本の卸売業者の強みとなっています。
例えば、ネジや工具などの細かく種類が多い製品を安定して仕入れようとした場合、在庫数を管理し、各メーカーに適切に発注を行うことは、小売業者にとって負担になるでしょう。
しかし、卸売業者を介すことで、在庫や配送を集約管理でき安定供給が実現できます。多数の商品を取り扱う小規模店舗にとっては、卸売業者と取引することは効率的なのです。
2-4.物流網の集約拠点としての役割がある
卸売業者は、物流網の集約拠点としても機能しています。例えば、小売業者が100のメーカーと直接取引をしている場合、毎週100台のトラックが納品にやってくる可能性があります。しかし、卸売業者が介在すれば、店舗にやってくるトラックは毎週数台程度で済むでしょう。
これは極端な例ですが、自社の配送網だけでは非効率になりがちなメーカーにとっても、卸売業がハブとなって商品をまとめ、各店舗に一括配送するメリットは大きいのです。配送コストを低減し、スピードアップや在庫削減も狙えるため、今後も卸売業者は重宝されていくことでしょう。
3.卸売業者間の競争を生き残るカギはIT化?
ここまで説明したように、メーカーの直接販売が増えても、卸売業がすべてなくなるわけではないと考えられます。しかし、IT化・DXの遅れから卸売業者の淘汰が進む可能性はあります。
ここでは、今後、生き残っていくためのカギとなる、IT化・DX推進による業務効率化や、課題解決の重要性について解説します。
3-1.「受発注システム」の活用がスタンダードに

これまでの電話・FAXなどでのアナログな注文方法に代わって、オンラインで受注を一元管理する「受発注システム」を導入することで、入力ミスや処理にかかる時間を大幅に削減できます。
電話をしながらメモを取ったり、届いたFAXを確認してパソコンに入力したりといった方法では、人の手作業が増える分、どうしてもミスが発生しやすくなり時間もかかっていました。しかし、受発注システムを導入することで、これらの課題を解決できます。
それだけでなく、リアルタイムで在庫や納期を共有しやすくなるほか、ミスが減ることで取引先からの信頼を得やすくなるメリットもあります。今後の卸売業界では「受発注システム」の活用がスタンダードとなるでしょう。
3-2.ECの活用により販路拡大も増える?
卸売業のIT化・DX推進としてもう一つ注目したいのが、BtoB ECなどの導入による新たな販路の開拓です。
BtoB EC(Business to Business Electronic Commerce)とは、企業間の取引をオンラインのECサイトで行う仕組みのこと。得意先以外も利用できるサイトにすれば、これまで物理的な距離の制約で取引が難しかったユーザーからも注文を獲得できるようになり、新たな販路の開拓につながります。
また、得意先のみが利用できるECサイトの場合も、取り扱い商品が多様な小売店や、小ロットでの取り扱いが多い小売店にとって、オンラインで商品の詳細情報を確認しながら発注できるメリットは大きいため、顧客満足度の向上に繋がる可能性があります。
卸売業者側にとってもメリットがあります。過去の顧客の購買データを活用し、ニーズに合わせた提案・営業がしやすくなるほか、消費者向けのECサイトを展開する第一歩にもなるのです。
5.まとめ
卸売業は一概に「なくなる」とは言えず、IT化やDX推進を進めることで新たな価値の提供も可能と考えられます。
アナログな業務フローをDXによって刷新することは、卸売業が将来も発展していくための要となるでしょう。近年は受発注システムや共同物流の取り組みが進み、膨大なデータを分析して提案営業を行う卸売業も増えています。
時代に合わせて業務フローを見直し、これまで培ってきたネットワークやノウハウを活かしながら、一歩先を行くIT活用に取り組む。そうすることが、卸売業が必要不可欠な存在として生き残っていく道筋になるはずです。
カシオの「BC受発注」で卸売・製造業の受注業務を効率化
カシオの「BC受発注」は、卸売業の受発注業務を効率化する受発注システムです。
得意先はスマートフォンなどから24時間発注が可能に。注文データは一元管理され、受注するとメールもしくはダッシュボードに通知が届きます。FAXやメールなどで起こりがちな見落としを防ぎ、ミスを未然に防ぎます。
受注内容を確認したら、「受注取り込み」機能を使って販売管理システムへデータを連携。手入力を減らすことで、業務にかかる時間を減らし、ヒューマンエラーの抑制に寄与します。
以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介しています。検討の参考にぜひご覧ください。
https://web.casio.jp/bc-order/
