
コラム

「按分」とは?意味や計算方法を分かりやすく解説
2025.04.25|最終更新日:2025.04.25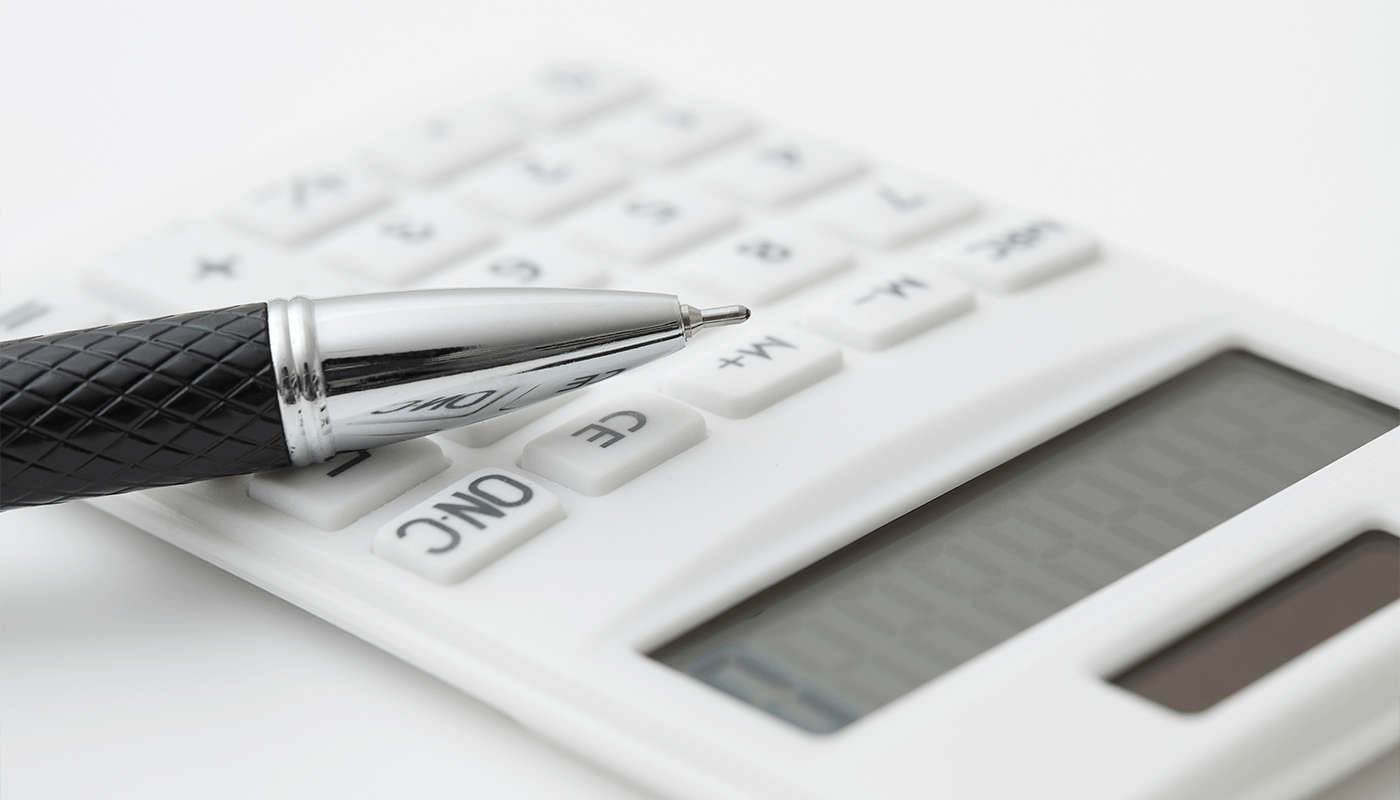
複数部署で一つの倉庫を共有する場合や、長期契約の保険料を年度ごとに割り振る場合など、さまざまな場面で「按分(あんぶん)」の概念が登場します。
では、この「按分」とはどのようなものなのでしょうか。ここでは、「按分」の基本や、按分が必要な場面、具体的な計算方法と計算例などについて解説します。
目次

1.按分とは
「按分(あんぶん)」とは、あらかじめ定めた比率をもとに、金額や数量を分けることをいいます。
分け方には基準があり、比率はケースごとに異なります。必ずしも均等になるわけではなく、この配分比率を「按分率」と呼びます。
按分の対比概念としてよく挙げられるのが「等分」と「折半」です。等分は人数などで均等に分ける手法を、折半は二つに半分ずつ分ける手法を指します。一方、按分は面積や使用時間、売上構成比など、合理的に設定した基準に応じて配分する点が特徴です。
1-1.按分と「等分」「折半」の違い

按分に似た言葉として「等分」が挙げられます。等分は「同じ割合で割り振る」考え方です。そして「折半」も半分に分けることを意味する言葉です。
一方の按分は必ずしも半々になるわけではありません。結果的に半々になることもありますが、基準を設けたうえで6:4や7:3など割合を決定します。

2.按分を使う場面
按分はビジネスシーンで使うことの多い処理で、二つの代表的な場面が挙げられます。
2-1.事業経費の費用按分
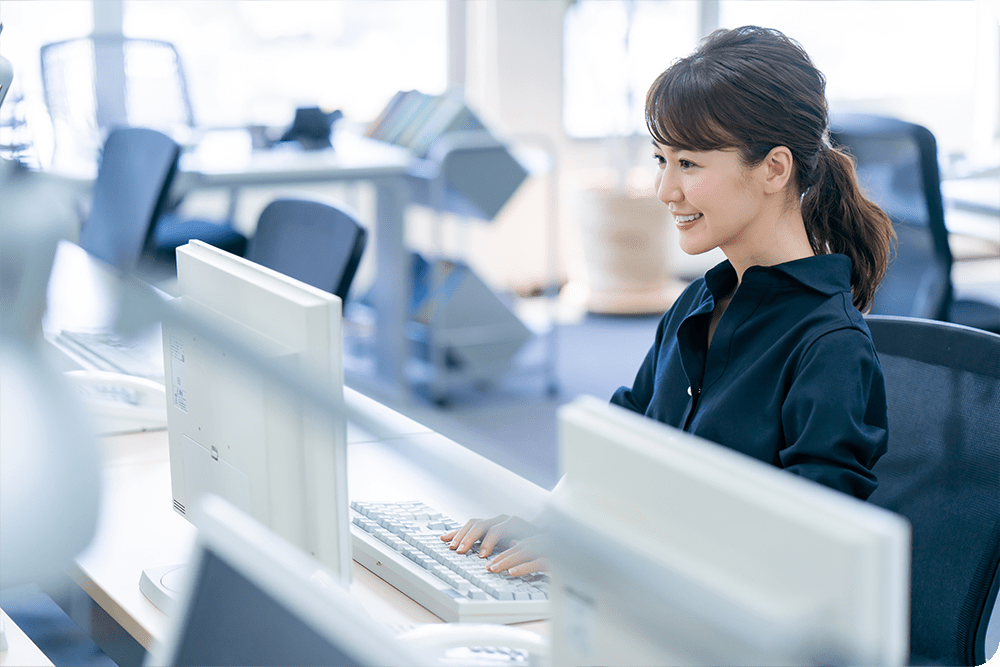
事業における経費の割り当てに按分が使われます。
例えば、倉庫の保管スペースやフォークリフトの稼働時間を複数事業部で共有しているケースです。この場合、それぞれの利用状況に応じて家賃や光熱費を配分します。
按分率を設定する基準としては、倉庫面積、取扱重量、作業時間などが考えられます。
2-2.個人事業主の費用按分
個人事業主が、自宅に事務所や店舗を構えている場合、家賃・電気代・通信費を事業経費と生活費に分ける必要があります。これを家事按分と呼びます。
税務調査で説明できる根拠として、部屋の床面積を元にした事業割合や、仕事で使用した時間などを日頃から記録しておくと安心です。
3.按分計算の方法
按分計算は「総額 × 按分率」の式で行います。按分率を決める方法としては、「割合基準」と「期間基準」の二つがあります。
3-1.基本的な按分計算
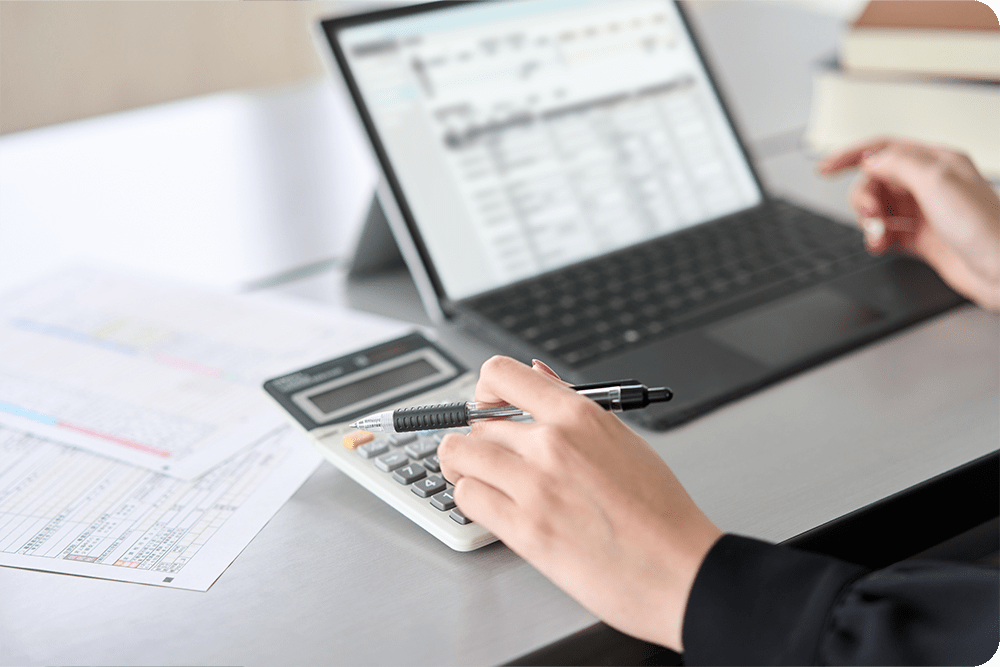
例1:1か月10万円の保険料を三つの事業で按分するケース
ここでは割合基準を採用します。売上が「事業A:70%」「事業B:20%」「事業C:10%」とした場合、保険料の按分額は、事業Aは7万円、事業Bは2万円、事業Cは1万円となります。
例2:3年分の保険料12万円を前払いした
このケースでは期間基準を採用します。保険料12万円を3年で均等に按分し、会計年度ごとに4万円計上します。
3-2.地代家賃の按分計算
例:個人事業主の自宅50平米のうち、20平米を事務所に使っている場合。家賃は月額10万円
地代家賃は、使用している床面積か時間のどちらかで按分計算しますが、より一般的なのは面積での按分です。このケースでは、事務所として使っている床面積は40%のため、按分率も40%となり、事業経費として計上できる家賃は4万円となります。
3-3.電気代の按分計算
例:1週間168時間のうち40時間を業務で利用。月の電気代が1万円の場合
ここでは期間基準を採用します。1週間の24%を業務で使っているため、按分率は約24%です。したがって按分額はおよそ2,400円となります。
3-4.売上の按分計算
例:100万円で受注した案件を、部門A:50%、部門B:30 %、部門C:20%の比率で担当した場合
一つの案件を複数の部署で行う場合、按分して予算と売上を管理するケースもあるでしょう。このケースでは割合基準を採用し、部門Aの売上は50万円、部門Bは30万円、部門Cは20万円となります。
3-5.サブスクの按分計算
例:1年間12,000円のサブスクリプション契約を結んでいる場合
ソフトウェア利用料などで、サブスクリプション型のサービスを年間契約している場合の計算です。月次の按分額は12,000円を12で割った1,000円です。ここでは期間基準を採用しています。
4.まとめ
按分は、費用と収益を合理的な基準で割り振るための会計手法です。面積や時間などから按分率を明確に設定することで、部門別の採算管理や、個人事業主の確定申告がスムーズに行えます。ここで解説した基本を抑えて、ルールを明確化し、税務やコストの最適化に役立てましょう。
受発注業務の効率化にカシオの「BC受発注」
カシオのBC受発注は、受発注業務の効率化に最適です。得意先から発注が来るとメールや画面上のアラートでお知らせするので、うっかり忘れることがなくなり、内容を確認したら「受注取り込み」をクリックするだけで販売管理システムに発注データを自動連携できます。
電話やFAX、メールなどバラバラな手段で発注を受ける必要がなくなり、入力にかかる手間も大幅に削減できます。さらに、受注した後の入力ミスも起こらなくなるため、得意先からの信頼もアップするでしょう。
発注を行う得意先は、パソコンやタブレット、スマートフォンから専用ページにアクセスして発注すればよく、得意先ごとの商品マスタも用意できるため、操作は難しくありません。従来の発注方法からの切り替えをお願いしやすくするツールも揃っており、スムーズに受発注業務のDX化を進められるはずです。
以下のページでは、BC受発注について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
https://web.casio.jp/bc-order/
