日本で活動をする外国人アーティストの中には、「外国人」としてカテゴライズされることに居心地の悪さを感じる人たちがいます。私たちは外国人が外国人としてではなく、ひとりのアーティストとして活動できる社会を作るために何ができるかを考えています。本イベントでは、日本社会でアーティストとして活躍するためには何が必要なのか、トークショーやディスカッションを通じて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
「多文化共生×アート」という大きなテーマのもと、かながわ国際交流財団MULPAの野呂田純一さんに取材を行いました。この取材をきっかけに「外国人アーティスト」としてカテゴライズされることに違和感を持つアーティストの存在を知りました。また、「カテゴライズされる外国人アーティスト」について着目し始めました。

イミグレーション・ミュージアム・東京(2019年度)で企画統括として活躍された、国際芸術創造研究科の助教、楊淳婷さんに取材を行いました。前回の取材を経てから、「外国人アーティスト」の大変さといったネガティブな面でのアプローチをしていましたが、この取材で外国人という立場を自らアイデンティティとして作品に生かすアーティストの存在を知りました。視野が広がり、再度チームでテーマを見直しました。
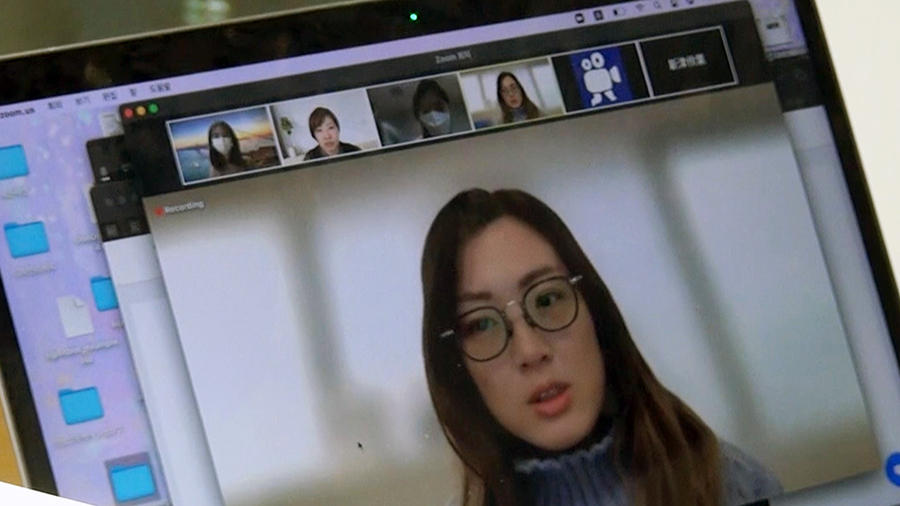
「外国人アーティストとしてカテゴライズされることに違和感を持つ人」と「外国人という立場をアイデンティティとして活用する人」の両者の存在を、参加者に共有するイベントを企画しました。そこで生まれた「他者性」という言葉について深掘りし、テーマについてのそれぞれの意識を確認するため、ディスカッションを行いました。

取材に協力していただいた野呂田さんと、武蔵野美術大学で油絵を専攻している留学生のパクさんをゲストにお招きし、イベントを行いました。今すぐ制度的な解決や変化ができなくても、共有することに意味があると考え、話を直接発信できる時間を多く設けました。トークショーや質疑応答では、参加者の方からも具体的なお話を聞くことができました。
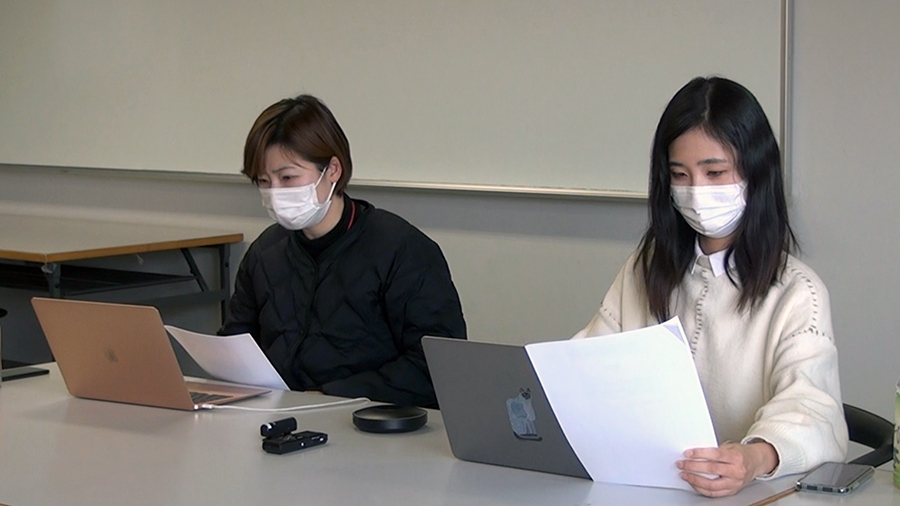
チーム|ブドウ
イム ダイン(デザイン情報学科、3年)
ジョン ユンビン(建築学科、2年)
南須原 莉子(芸術文化学科、3年)
新津 伶葉 (芸術文化学科、3年)
金 度希(カシオ計算機)
南須原 莉子
(なすはら りこ 芸術文化学科・3年)
ゲストの方々や参加者の方々による、貴重なお話しをたくさんいただくことができました。外国人アーティストというカテゴライズ、自分自身の中にあるアイデンティティー、そして外国人という立場で生まれる他者性。そういった問題に直面した時にただ答えを見つけるのではなく、まず存在を知り、考え、共有することに意味があるのではないでしょうか。そういった行動が、共生社会をつくる上で大切であり、はじめの一歩になるのだと思います。